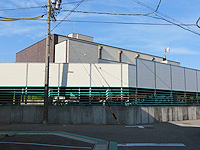diary 2019.5.
diary 2019.6.
■2019.5.31 (Fri.)
教育実習生のお疲れさま会なのであった。教科は英語で、サッカー経験者ということでサッカー部の面倒も見てくれて、
こちらとしてはお世話になりました感がある方である。部員をはじめ生徒たちも彼の懸命さに応えていた感じ。
僕は自分の授業が忙しくて一度も見学に行けなかったが、その懸命さで着実に磨いていけばいいんじゃないでしょうか。
いちおう自分がもはや英語については特殊な存在となってしまっているのは自覚しているので、それくらい。
とにかく学校には多様な先生がいる方がいいので、ほかの先生にないものを武器にしてがんばってほしいです。
■2019.5.30 (Thu.)
『深夜!天才バカボン』。『おそ松さん』(→2017.9.27/2018.9.3)の二匹目のドジョウを狙ったんだろうけど、
バカボンの舞台化(→2010.7.26)で十分な実績のある細川徹を監督に迎えて万全の態勢としたのだろうけど、
なかなかの爆死っぷりだったようで。『おそ松さん』でハードルが上がっている状況は逆風でしかなかったですなあ。
まず申し訳ないのだが、バカボンのパパ役の古田新太の声にげんなりしてしまった。申し訳ない。
でもオレにとってはバカボンのパパは富田耕生以外ありえないので、どうしても入り込めないのである。申し訳ない。
そんな個人的事情はさておき、中身について。決してつまらないわけでもないのだが、ギャグの打率は低かったなあと。
もっとじっくりギャグを練ってからやるべきだったと思うのである。ところどころのクリーンヒットがつながらず惜しい。
結局のところ下ネタに寄ってしまったり、こんな意外な人が出てきたよ!に頼ったり、という安易さが敗因だと思う。
おそらく細川さんの感覚だとぜんぶ面白いのかもしれない。でもその波長が大方の視聴者とシンクロするわけではない。
これまでの細川さんの実績がかえってギャグの多様性を奪っていたのではないか。独りよがり感があったんだよなあ。
公的な二次創作(→2007.11.9)ではあるものの、ちょっとバカボンの私物化がキツかった。お客さんを見てなかったよね。
まあ逆を言えば、多様なギャグを一人で生み出して膨大な人数を笑わせてきた赤塚不二夫がとんでもないってことだが。
あと色づかいがおかしくないか? 『おそ松さん』のポップさの影響が悪い方にエスカレートしているように感じる。
これで『天才バカボン』というコンテンツが封印されてしまうことがありませんように……。いやホントそれだけ。
■2019.5.29 (Wed.)
まちがって朝早すぎる時間帯に起きると『おはよう!時代劇』で『暴れん坊将軍』をやっていて、
思わず見入ってしまうことがある。皆さんもないですかね、そういうこと。まったくないとは言わせないぜ。
しかしあらためてじっくり『暴れん坊将軍』を見てみると、いろいろ考えてしまうではないか。
まず、異様にテンポがいい。確かに定番の時代劇は話の筋が単純明快で、変な伏線などよけいなお世話なのだ。
そのため展開が強引でツッコミどころも多いけど、「洗練」されたことで様式美ができているのがまた面白い。
良く言えば「マンネリの美学」。そのマンネリというより職人芸か、そしてそこに至るまでの工夫を味わうものなのだ。
安心して見られるといえば確かにそうだけど、このお約束が延々と続く(『暴れん坊将軍』は全832回)のは少々つらい。
批判的に見れば、なんとかなってしまう展開は和辻哲郎『風土』(→2008.12.28)におけるモンスーン型対応というか、
家父長的な無責任さ(→2010.2.3)に通じるようにも思う。繰り返されるルーティンが絶対的なものとなってしまって、
登場人物たちが自らそのルーティンにハマりにいっているようにすら思える。それが上述の様式美ってことだが。
どんな波乱も絶対的な日常へと戻っていくという根拠のない楽天性。時代劇の構造は、まさにそれを具体化したものだ。
時代劇が貴重な文化であることは間違いないが、その困った面も社会学的にきちんと検証すべきだと思う。
それにしても時代劇が衰退して久しいが、それと昭和的「(映画)スター」(→2018.12.20)の不在は関係が深そうだ。
でも日本の家父長制の困った面は今もしっかり残っている。「オヤジ」がいなくなったのに、家父長制が残っている。
それはただ無責任でしかない社会だ。時代劇の衰退は、なんだか日本が悪いとこどりして変化している象徴にも思える。
■2019.5.28 (Tue.)
ネタがないので、すっかり書き忘れていた2年くらい前のことを今さらだけど書いておく。
AKBの衣装の本が大いに話題になったじゃないですか。正式なタイトルは『AKB48 衣装図鑑 放課後のクローゼット』か。
すでに皆さんお気づきのとおり僕はAKBについてはかなり批判的なスタンスなのだが、さすがにこれは気になった。
わりと前向きに、買ってみようかなあなんて思いつつ本屋に行って、パラパラとめくってチェックしてみたのである。
で、感想は「どの衣装もなんだか品がねえなあ」。それで終わり。残念ながら、買うに値しなかった。
アイドルの衣装ってのも絶対に奥が深い世界で、僕みたいなブサイク軍には想像もつかない深淵があるんだろうけど、
ファッションのわからん僕が言うのもおかしいけど、AKBの衣装については本当に品というものを感じなかったのだ。
いやそもそもアイドルの衣装に品が必要なのかどうか、そもそも僕ごときに品を語るだけの資格があるのかどうか、
いろいろと考えなければいけないポイントはある。それらをすっ飛ばしたうえで思ったのだ。「品がねえなあ」と。
そういえばタカラヅカを観劇したときに、「タータンチェックがAKB風」なんてことを感じたっけ(→2012.2.26)。
まあ、記号なんですけどね、衣装ってたぶん。その記号性をどのように編集するかって話なんだけど、
その編集センスに品を感じなかったということなのだ。ただ安っぽいだけじゃなくて、ダウングレード感がある。
『ラブライブ!』の感想で「『スター』のネオテニー(幼形成熟)としての『アイドル』」と書いたけど(→2018.12.20)、
その矮小化されている感じが衣装にそのまま出てしまっているというか。それを僕は「品がない」と言語化したわけで。
ファッションのわからん人間が偉そうなことをほざいて申し訳ないが、これ以外の語彙が出てこないのである。
じゃあ品のあるアイドル衣装って何よ、と言われるとわからない。わからないけど、AKBの衣装には品を感じない。
なんだか本当にすいません。でもそう思っちゃったんだからしょうがないじゃないか。申し訳ない。でも品がない。
■2019.5.27 (Mon.)
今さらオリンピックなんぞに権威を感じている時点で阿呆である。日本は時代錯誤の阿呆が多すぎる。
■2019.5.26 (Sun.)
わがサッカー部の集大成となる区大会である。日程と会場の都合があるとはいえ、炎天下で一日2試合は大いに不満。
しかし文句を言っても始まらないので(専門委員には言ったけど)、あれこれ声かけして準備を進めていく。
ベンチではコーチ、そして教育実習に来ている先生とともに、固唾を呑んで試合を見守る。
人数不足で慣れない1年生を起用せざるをえないハンデはいかんともしがたく、いいプレーを随所に見せるも2連敗。
本当にいいチームだったのに、早々に引退が決まってしまった。部員たちは最後まで全力で走りきっていたし、
それぞれの持ち味をしっかり発揮してくれたのだが。それでも勝てなかった。もう本当に悔しくて悔しくて。
部員たちは全力を出しきったからかどこかすっきりしているんだけど、それをとやかく言うつもりもまったくないけど、
僕はもう悔しくて悔しくてたまらない。2年前の先輩たちが見た光景を彼らに再び見せることができなかったのが悔しい。
人数がやたらめったら多かったあの代にも絶対に引けを取らない才能が揃っていたのに、勝てなかったのが悔しい。
「勝たせてあげられなかった」なんておこがましい感情は一切ない。才能に対して正当な評価がなされなかったことが、
たまらなく悔しいのだ。しかし怒りを向ける矛先などそもそも存在しないので、怒りはなく、ただただ悔しい。
自分のことより悔しい。こんなに純粋に「悔しい」という感情だけが全身を支配することは今までなかったし、
これからもないだろう。7年前にも悔しい思いをしたが(→2012.6.10)、時間が経ってあの経験は誇りにもなっている。
でも今回の悔しい感情はどこまでいっても昇華されようがない。悔しさがそのまま石のようになって体の中に残り続ける。
そういえば小林まこと『柔道部物語』に「どんなに努力しても むくわれないこともあるのか!!」 というセリフがあるが、
もう本当にそういう気分。オレは努力してないけど、外から見ていただけだけど、そういう気分。すっきりしねえええ!
■2019.5.25 (Sat.)
本日はサッカー天皇杯の1回戦ということで観戦に行きたかったんだけど都合つかず。残念である。
それにしても何が凄いって、山形県代表である。山形大学医学部サッカー部。4年ぶり3回目の出場って凄すぎないか。
ちなみに山形大学の体育会サッカー部は別にあって、こちらは準決勝敗退の3位。どっちも凄いが、いやはや……。
しかも医学部サッカー部は4年前の天皇杯では当時J1のモンテディオ山形と対戦して、前半40秒でゴールを決めたとか。
高校時代から全力でサッカーをやって、卒業後は山形大学医学部に入って天皇杯を目指す、なんて人生もあるわけだ。
世の中は広い。凄い人がいっぱいいるなあと呆れるのであった。自分の怠惰な人生が情けなくなってくるなあ。
で、山形大学医学部サッカー部は神奈川県代表・桐蔭横浜大学に0-8で敗れてしまった。でも尊敬しかないですよ。
■2019.5.24 (Fri.)
この3月に卒業した生徒会長(サッカー部ではGKだった)、高校でクイズ研究会に入っちゃったとのこと。
オレのせいかね……。オレのせいでクイ研人生歩ませちゃったのかね……。まあ、存分にクイ研人生楽しんでくれい。
■2019.5.23 (Thu.)
甘やかされた半人前が対等な口を利こうと思うな。──そんな言葉が思わず口から出かかった。
わからないのは、自分をまるで客観視できていない今時の中学生にみられる根拠のない自信である。
いったい何様のつもりなんだろう。他人の能力を把握できないレヴェルなのに、なぜそんなに自信が持てるのか。
僕が中学生のときには相手の力を見誤って恥をかくのがイヤだったからできるだけ謙虚に接したし、
実際にどの先輩・先生にも尊敬すべき部分があったので、人間的に合わなくてもその部分には敬意を表した。
そんな僕には、大した能力もないくせに一丁前な態度をとれる神経が理解できない。見ているこっちが恥ずかしい。
そういうやつに限って「褒めて伸ばすべきだ」なんて臆面もなく主張するのだ。褒める部分なんてないだろ、お前。
プライドをきちんと折られて強制的に謙虚になる経験がないと、伸びる物も伸びないのだ。これが絶対的な真理だ。
バカにはバカですと言ってやるのが親切であるはずだが。お前はバカですよとちゃんと教えてあげるだけ優しいのだが。
■2019.5.22 (Wed.)
しかしゴシックホラーってのはハードロックやヘヴィメタルとどうして相性がいいのか不思議である。
これはブラック・サバスだとかジューダス・プリーストだとかそっち方面の名前のせいなのか、
それとも70年代のファッションのせいなのか。単純にそれらの時代が噛み合ったということなのかもしれんが。
しかし僕としては潜在的な相性のよさが先にあり、それでそっち方面だったりあのファッションだったりな気がするのだ。
よく考えれば、ゴシックホラーとハードロック/ヘヴィメタルの間には、何の必然性もないはずなのだ。
それなのに、十分な時間が経過した今でも両者を違和感なく受け止められる。これは本質的なものがあると思う。
その間を商業的に上手く衝いたのがヴィジュアル系ってことになるんだろうけど、流れは連綿と続いている。
ゲームではコナミの『悪魔城伝説』が代表格ですかな。このBGMがまたハードロック/ヘヴィメタルに合うのだ。
単なる社会現象ではなく、心理学的か社会学的に十分捉えられるテーマだと思う。どうなんですかね、潤平さん。
■2019.5.21 (Tue.)
久しぶりの大雨である。やっぱり一日中降り続くというのは精神的にまいるねえ。
■2019.5.20 (Mon.)
午前中は浦和の埼玉県庁へ。過去問をひたすらデジカメで撮影していく作業に追われる。
そして午後は部活である。3年間苦楽を共にしてきた部員たちの集大成となる夏季大会が、今週末に始まるのだ。
小規模校ゆえに人数不足で苦しんできたが、3年生の能力だけで言えばブロック大会、そしてその上が見えるレヴェル。
なんとしてもその力にふさわしいだけの結果を手にしてもらいたい。顧問も静かに燃えておるんですことよ。
■2019.5.19 (Sun.)
本来であればゴールデンウィークの旅行で伊勢湾周辺をあちこちまわる予定だったが、天気が悪くて果たせなかった。
それで突発的に日帰りリヴェンジを敢行してしまったのである。夜行バスで近鉄四日市駅に転がり出ると、伊勢市駅へ。
うむ、久しぶりである(→2019.5.1)。……そんな小ボケをかましつつ、外宮をスルーして伊勢市役所へと向かう。
しかし伊勢に来ておいて神宮をスルーするのは、参拝してから3週間足らずとはいえ、なんとも罪悪感がある。



L: 伊勢市役所本庁舎。位置的には外宮と宇治山田駅の中間にある感じ。道路の幅があまりないので撮影しづらい。
C: ぎりぎりなんとか正面から撮ってみる。 R: 南西から見たところ。しかしこだわりを感じさせない庁舎だ。
前回訪問時には細かいことがわからなかったが、今回あらためて調べてみたら内部のリニューアルを終えたばかりで、
1965年竣工というデータが出てきた。しかし隣接する東館などの細かいことはやっぱりわからなかったのであった。



L:
本庁舎に隣接する東館。 C: さらに東に隣接する伊勢商工会議所。これは北東から見たところ。 R: 東館の背面。
伊勢市役所の本庁舎は背面となる北側から見てもほぼ同じデザイン。あんまりこだわりがない建物だなあと思いつつ、
正面に戻ったら足元にやや和風テイストの欄干が付いていた。そこだけこだわるか? よくわからない庁舎である。



L: 背面を北東から眺める。 C: 駐車場を挟んだ背面。 R: 北西から。何やら新しい建物がくっついている。



L: 西側の側面。 C: 正面側、よく見たら欄干が付いている。うーん、意味がわからん。 R: エントランス。
 駐車場の端に残る御師邸跡の塀。おかげ参りの文化(→2006.8.30)も今は昔か。
駐車場の端に残る御師邸跡の塀。おかげ参りの文化(→2006.8.30)も今は昔か。
そのまま宇治山田駅へ直行。天気がよくなってきたのであらためて撮影。しかし幅があってすっきり撮影できない。
詳しいことは前に書いたとおりだが(→2012.3.31)、相変わらずVIP向けの威厳がビンビン漂っているのであった。



L: 宇治山田駅を北西から眺める。 C: 南西から。 R: 駅舎内がまた荘厳なのよね。
宇治山田駅から再び近鉄に揺られ、鳥羽駅で乗り換えると鵜方駅で下車。あらかじめレンタサイクルを予約しておいたが、
係の方が休日にわざわざやってきた感じでなんだか申し訳なくなる。でも今回の目的地はレンタサイクルが必須なのだ。
むしろ心置きなくフル活用させていただくべきなのである。手続きを済ませると、東に向かってペダルをこぎだす。
周りの景色は元気に生い茂る緑が主役という感じ。いかにも温暖な海がすぐそこって感じの中を抜けていく。
道路は郊外社会のそれで、複雑な地形のわりには幅がけっこう広くて、大型車両も気持ちよく走っているのがわかる。
おかげで自転車としても走りやすい。やがて国府というエリアに入る。その名のとおり、かつて志摩国の国府だ。
「志摩国分寺」という案内板があったので寄ってみる。規模は大きくないが、本堂は実に端正なつくりである。
1843(天保14)年の築で、志摩市の指定文化財。彫刻もいいが、破風の上の瓦に乗る小さな麒麟たちが印象的だ。



L: 志摩国分寺の山門。 C: 抜けると本堂。端正である。 R: 細かいけど麒麟がいるのがわかりますかね。
参拝を終えて少し進むと、今度は「渡鹿野島 渡船のりば」の文字。おお、渡鹿野島か!なんて思うのであった。
江戸時代からすごかったらしいが、バブル期にはもっとすごかったそうだ。でも今はぜんぜんすごくないそうで、
行ったところでどうしょうもないのでスルー。そんな暇があったらひとつでも多くの市役所を訪れたいのだ。
 阿児町安乗に到着である。
阿児町安乗に到着である。
というわけで、志摩半島の端っこ(のひとつ、リアス海岸だから端っこと呼べる場所がいっぱいあるのだ)、
安乗(あのり)に到着なのだ。なぜわざわざここまで来たのかというと、こちらに鎮座する安乘神社の御守が面白い、
という記事を見たから。御守のためなら離島を原付で走ったり山に登ってついでに捻挫したりする男ですから、僕は。



L: 安乘神社にいざ参拝。 C: 参道を行く。いかにも漁港の神社といった風情。 R: 拝殿。
安乘神社の名物となっているのは「波乗守」である。「開運の波に乗る」とのことで、さっそく頂戴する。
そういえば上総国一宮・玉前神社もサーフィンの本場ということで、同じ系統の御守があったっけ(→2018.10.7)。
しかしこちらにもなかなかの裏付けがあるのだ。もともと安乗は「畔乗」「阿苔」という表記だったそうだ。
九鬼嘉隆が朝鮮出兵の際に船が進まなくなってしまい、安乘神社に祈願したところ無事に航海ができたそうで、
以来「安乗」に改めたという話(もともと安乗崎は航海上の難所)。そして御守は鮫を波とともにデザイン。
これは祭神の玉依姫命は鮫だったという伝承にもとづいているのだが、実に見事なディフォルメぶりである。
観賞用と保存用に2体頂戴してしまった。いや、これは人気出るだろうなあ。わざわざ訪れた甲斐があった。


L: 本殿。もともとは八幡神社だったが旧安乘神社を合祀して、新たな安乘神社となったそうだ。
R: 安乗崎に建設された砲台の砲身が保存されている。しかしなぜ赤く塗っているのかはわからない。
神社からさらに先、安乗崎の先端へと向かう。安乗岬園地という広場になっており、端っこには安乗埼灯台。
とりあえず周辺を歩きまわるが、ふつうに芝生の広場だ。「きんこ芋工房 上田商店」の土産物店があり、中に入る。
「きんこ芋」とは希少なサツマイモのハヤトイモを煮て切って干したもの。まあつまりは干し芋である。
干しナマコの金ん子(きんこ)に形が似ているのでその名がついた。ちなみにベニハルカだと「ぎんこ芋」となる。
こりゃいいや、と職場向けのお土産として購入したのだが、女性の先生方には非常に評判がよかったのであった。



L: 安乗岬園地。 C: 端っこの方はこんな感じ。 R: こちらは安乗埼灯台資料館。
では安乗埼灯台へ。四角柱の灯台はなかなか珍しい気がする。しかも安乗埼灯台、中に入れる参観灯台なのだ。
高所恐怖症だけど好奇心が圧勝で上っちゃう。ちなみに現在の灯台は2代目で、1948年竣工とけっこう新しい。
初代は1873年(明治6)年の築で、東京の船の科学館に移築保存されているとのこと。いずれ行きたいものである。



L: 安乗埼灯台。見事に四角である。 C: 中も見事に四角なのであった。 R: 安乗岬園地側を眺める。岬だなあ!



L: 的矢湾を眺める。リアス式を味わうには正直もうちょっと高さが欲しいかな。なお、渡鹿野島はぎりぎりで見えない。
C: 北の菅崎。ここから左が的矢湾となるわけだ。 R: 東の太平洋。確かにこれは航海の難所っぽいなあ。
堪能すると鵜方駅へと戻るが、そのまま素直に自転車を返却するはずがないのだ。志摩市役所をあらためて撮影。
前回訪問時は天気がよろしくなかったので(→2012.3.31)、リヴェンジするのである。晴天の下で撮るのは気分がいい。



L: あらためて志摩市役所。まずは北東から。 C: 一段下にある駐車場から見たところ。 R: 北から仰ぎ見る。



L: 北西から。 C: 近鉄志摩線の線路を背中に西から見た側面。 R: 線路越しに距離をとって見たところ。



L: 南西から。少し高低差のある土地なのだ。 C: 南から見た背面。 R: 南西から。以上で一周完了である。
素敵な御守に灯台に市役所と、思う存分楽しませてもらった。丁寧にお礼を言ってレンタサイクルを返却すると、
近鉄で鳥羽駅まで戻る。ところが困ったことに、鳥羽に着いたところにわかに天気が悪くなり、雨が降り出した。
とりあえず毎度おなじみ「メルヘン」でうどんを食い(あおさうどんはこないだ食ったので今回はあさりうどん)、
様子をうかがう。そのうち雨の勢いが弱まってきたので、思いきって鳥羽1番街のかもめレンタサイクルを借りる。
僕だって雨の中を遠出するのはイヤなので、危なくなったらすぐ返しますってことで慎重に行動を開始する。
まず最初に向かったのは、やっぱり鳥羽市役所。着いた頃には雨はやみ、とりあえず灰色の空の下で撮影。
そういえば前回(→2012.3.31)も雨の中で撮ったなあと思う。でも空はだんだん明るくなってきており、いい流れだ。
撮影を終えると国道を南下して加茂川右岸へ。ここから安楽島はわりとすぐだが、その前に行っておきたい場所がある。



L: 鳥羽市民文化会館。1972年竣工で、設計は千代田建築研究所。しかし昨年12月29日をもって閉鎖となったそうな。
C: 鳥羽市民体育館。こちらも千代田建築研究所の設計で、竣工は1973年。8月から改修工事を行うそうで、なんとも対照的。
R: 福良の漁港。すっかり天気は回復して、いったいあの雨はなんだったんだと思う。賭けに勝ったのでうれしい。
急激に天気が回復してきたとはいえまだ濡れている箇所もあるし、複雑なリアス式の海岸線を自転車で走るのは面倒だ。
邪魔にならないところに自転車を駐めると、福良のバス停からバスに乗り込む。目指すは鳥羽市立海の博物館。
もともとは市街地にあったが「どんなモノでも集める」方針で資料を保管しきれなくなり、それで今の場所に移転した。
おかげで行くのが大変である。内藤廣建築設計事務所の設計で1992年に再オープンし、公共建築百選に選出された。
しかし経営難により、おととし鳥羽市に移管されて公立の施設となった。バブルで市が建てた、ではなかったのが意外。



L: 海の博物館。かつての建物は塩害に苦しんだそうで、極力金属を用いないスタイルに。おかげで展示とマッチした外観に。
C: エントランス。 R: 中に入るとまず魚屋を再現したコーナー。なるほど、御食国(→2010.8.20)以来の誇りがあるわけだな。



L: 展示A棟。大空間をそのままにたくさん並べるとは斬新。 C: 反対側。 R: 2階の展示。これは漁民の信仰のコーナー。



L: 展示A棟とB棟の間には池がある。 C: 展示B棟の手前から池越しに眺める展示A棟。 R: 妻側はこんな感じ。
海の博物館の特徴は、広い土地を利用して建物を6棟に分散配置している点。敷地には微妙な高低差があるが、
建物内で2階に上がればそのまま次の建物の1階に入ることができるような、バリアフリー的工夫がなされている。
だから意外と移動にストレスがない。むしろ膨大な展示を連続的に味わうので、体より頭が疲れるくらいだ。



L: 敷地の高低差。上にあるのは重要文化財収蔵庫。建物の分散具合はのんびり散歩するのにいい感じでもある。
C: 重要文化財収蔵庫から眺める展示B棟(この右に池、そしてA棟があるわけだ)。 R: 展示A棟前から見たB棟。



L: 展示B棟の内部。こちらは地元・伊勢湾の漁が中心のようだ。 C: 大空間を生かした展示である。
R: ちょうど中学生の校外学習だか修学旅行だかをやっている真っ最中なのであった。日曜日に大変ですなあ。



L: この一角は海女さん特集。 C: 九鬼嘉隆。説明に「日本最初の水軍大将」とあるが、それは朝鮮出兵時の話。
R: 捕鯨コーナー。銛を使った捕鯨は熊野水軍から転じた専門の漁師が確立したそうだ。しかし展示はあっさりめ。
体験学習館の2階は特別展示室になっており、企画展「ギョコレ(漁村コレクション)」と称して衣類を展示。
地味なふだんの衣服から祭りの衣装まで幅広く取り揃えているのであった。大漁旗がまたカラフルでよい。
いや、僕としてはむしろ大漁旗のデザイン研究とか気になるのだが。やはり地域で特徴とかあるのだろうか。
(ミュージアムショップでは古い大漁旗の一部を使ったバッグやケースを売っているが、全体像はつかめない。)



L: ウナギ石倉漁。ちなみにこのウナギのぬいぐるみ、ミュージアムショップで販売中。30年近く売っている人気商品とか。
C: 体験学習館。こちらの2階が特別展示室となっており、企画展はこちらでやっている。 R: ギョコレ。華やかである。



L: 中庭を抜けた先のフォトギャラリー。 C: 振り返るとこんな感じ。左が重要文化財収蔵庫、右が展示A棟。
R: 重要文化財収蔵庫。各棟で湿度に差をつけて保管しているそうだ。いちばん奥にあるのが「船の棟」の入口。
重要文化財収蔵庫は3棟あるが、そのうち最も奥にある「船の棟」のみが公開されている。もちろん見学。
土足厳禁ということで靴を脱いでお邪魔すると、そこには無数のさまざまな木造船が並んでいた。思わず圧倒される。
収蔵されている船は80隻ほどだそうだが、広大な空間を埋め尽くしていて数の感覚が完全に麻痺してしまう。
この1隻1隻に、濃厚な物語が存在しているのだ……。ただただ、海洋国家の船の歴史に茫然とするのみである。



L: 船の棟の玄関。丸木舟から始まるのが非常に正しい。 C: 1隻1隻、それぞれに物語があったと思うと眩暈がする。
R: そんな船たちが大空間を埋め尽くす。山国育ちで気にすることがなかったが、船の歴史の厚みに衝撃を受ける光景だった。
せっかくなので、併設されている「カフェあらみ」でランチをいただく。さすがにシーフード系が充実していて、
アオサなどの海藻やシラスなどで定番軽食メニューがうまくアレンジされている。ちなみに伊勢うどんもある。
迷った末、海の幸牡蠣カレーに決定。おいしゅうございました。あっという間に平らげてしまったよ。


L: カフェあらみ。エントランス脇、展示A棟の向かいにある。 R: 海の幸牡蠣カレー。そりゃ旨いに決まっているだろう。
というわけで、帰りのバスの時刻までしっかり堪能したのであった。実家への土産にウナギのぬいぐみも買ったし。
似た施設に高松市五色台の瀬戸内海歴史民俗資料館があるが(→2015.5.4)、どちらも空間的な工夫が非常に面白い。
高松の方は高低差のある山の上に位置し、「海賊の城」をイメージした建物が連続的につながっているのが特徴である。
1973年竣工の建物は、モダニズム建築がポストモダニズムへと移行する中で土着性(ヴァナキュラーってやつ)を軸に、
品性を問いながら設計されていたと思う。個人的には飽きのこない展示室配置と採光への配慮がかなり印象に残っている。
それに対し、海の博物館は木材を前面に押し出した土着性を強調し、建物をつながず分散配置のままとしている。
どちらがいいかは個人の好みだろうが、比較によって20年間の建築史的な変化を分析するのはけっこう意義がありそうだ。
 車窓から見た生浦(おおのうら)湾。浦村かきを養殖中で、道路沿いに店がいっぱい。
車窓から見た生浦(おおのうら)湾。浦村かきを養殖中で、道路沿いに店がいっぱい。
福良に戻ると再び自転車にまたがり、東の安楽島へ。志摩国一宮・伊射波神社(→2013.5.5)の御守チェックなのだ。
前回はバスでのアクセスだったが、いざ自転車で来てみると時刻を気にしなくちゃいけないバスよりずっと便利。
鳥羽駅からはもっと距離がある印象だったけど、ぜんぜんそんなことはないのであった。かなり手軽に来られる。



L: というわけで安楽島に到着。 C: 安楽島舞台。 R: それでは参拝をスタートするのだ。



L: 前回参拝時にいろいろ撮っているので今回は簡略版で。それでもこの海はまた写真を貼っちゃうなあ。
C: 海岸に面する一の鳥居。 R: 石畳がしっかりしている箇所はこんな感じ。でもこの後は石段混じりの山道に。



L:
伊射波神社に到着。 C: 社殿の向かいはこんな感じ。 R: 正面から拝殿を見たところ。前回も撮ったなあ。
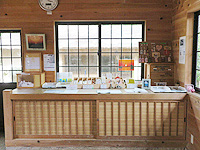


L: 拝殿内の授与所コーナー。 C: 御守の種類が激増している! うれしい悲鳴をあげつつ頂戴する。 R: 充実しているなあ。
6年ぶりの参拝だが、前回の御守が3種類だけだったのに対し、種類も色も一気に増えていたのであった。
これはわざわざ来た甲斐があった。しかしお財布的には大変。うれしい悲鳴をあげつついろいろ頂戴していく。



L: 本殿を横から眺める。現在の社殿は2001年竣工。まあ伊射波神社は建物云々より岬に鎮座していることが重要だからなあ。
C: 加布良古崎突端の領有神(うしはくがみ)。賽銭箱が横に移って見やすくなった。 R: 失礼して領有神をクローズアップ。



L: 朝日の遥拝所には「奇跡の窓」とか俗っぽい名前がついたようだ。ベンチが整備されたのはいいことだと思う。
C: まあなんだかんだできちんと眺めるんですけど。 R: 手前の賽銭箱。なんだかほっこりしますなあ。
帰りは再び鳥羽市役所へ寄って、青空の下でリヴェンジ撮影。1962年竣工、設計は建築綜合計画研究所とのこと。
よく考えるとこの時期の建物にしては珍しく、耐震補強がされているように見えない。ちょっと不思議である。



L: 鳥羽市役所。特徴的な形である。 C: 近づいてみる。中央の円柱は螺旋階段。 R: 曇りのときに撮ったエントランス。



L: 振り返ると鳥羽城家老屋敷跡。 C: 北西から見上げる鳥羽市役所。 R: 西から見た側面。



L: 南西から見上げる。 C: 南から。背面っていうのかな。 R: さらに近づいて撮影。
これで鳥羽市内の探検は終了。自転車を返却する際、晴れてよかったですねーという話になる。いや、本当によかった。
しかし残念ながら鳥羽1番街でのんびりお土産を見繕っている暇などないのだ。中之郷駅の辺りまで走って戻ると、
鳥羽港のフェリーターミナルへ。すでに乗船手続きは始まっているどころか、もうすぐ終わろうというところ。
急いで豊橋・鳥羽割引きっぷを購入して伊勢湾フェリーに乗り込む。そう、今回は船で伊勢湾を横断して帰るのだ。
 それでも鳥羽港フェリーターミナル内を撮影する性(さが)よ。
それでも鳥羽港フェリーターミナル内を撮影する性(さが)よ。
僕が最後の乗船客で、船は出航。デッキに出て風を受けながら景色を眺めるが、鳥羽の港町がどんどん遠くなる。
今回は温泉に浸かる余裕がないのが残念だったが、こうして船で揺られているとまあそれはそれで、という気分になる。
東京へ戻るのにわざわざフェリーで伊勢湾を横断するという選択肢も、純粋に面白いものではないか。



L: 出航する伊勢湾フェリー。 C: 鳥羽の街がだんだん遠ざかる。 R: ミキモト真珠島。そういえば行ったことないなあ。
答志島と菅島の間を抜けると海に出た!という感じになるが、それでもこの先にある神島までが三重県鳥羽市。
山国育ちの僕には海の生活が想像できないが、フェリーに乗ったことでその一端に触れることができた気がする。
 記念に撮影。3隻あるフェリーだが、今回お世話になったのは知多丸。
記念に撮影。3隻あるフェリーだが、今回お世話になったのは知多丸。
神島の横を抜けると、いよいよ行く手に伊良湖岬が現れる。2年前の経験と現在がようやくつながった(→2017.12.29)。
あのときはむやみやたらに伊良湖岬の先端を目指したが、その意味を今日の伊勢湾フェリーでやっと回収できた。



L: 神島。三島由紀夫『潮騒』の舞台(旧称である「歌島」という名前になっている)。読んだことなくて申し訳ない。
C: 伊良湖岬が見えてきた。2年前の記憶がリンクする。 R: 岬の突端。伊勢湾海上交通センター、行ったなあ。



L: 伊良湖岬に到着。1時間弱だがいい経験だった。 C: 伊良湖クリスタルポルトを海側から見たところ。
R: 知多丸。お世話になりました。やはり定期航路を味わうのはその土地の日常が垣間見えて面白いものである。
田原駅行きのバスが出るまで30分ほど待機。バス停近くに野良猫たちがいたので一緒にひなたぼっこして過ごす。
特に人に馴れている感じがそんなにないのは伊勢湾フェリーの利用客がそんなに多くないからか。ちょっと残念。
 かわいいものである。こっちに来てくれればもっとかわいいのだが。
かわいいものである。こっちに来てくれればもっとかわいいのだが。
18時を過ぎてバスに乗り込み、田原駅に着いた頃にはだいぶ暗くなっていた。渥美線に淡々と揺られて新豊橋へ。
豊橋から浜松まで東海道線でのんびり進み、浜松からは「ぷらっとこだま」。だいぶお安く東京に帰ることができた。
結果的に今月1日の神宮参拝と分けたことが大正解になった一日だった。懸案事項を一気に片付けられて大満足である。
■2019.5.18 (Sat.)
体育祭本番なのであった。本当によくがんばったなと全力で褒めてあげたい。
生徒がバンバン動いてくれるので、こっちは毛利敬親のように「そうせい」と言うだけ。
それですべてがスムーズに動くというのは感動的なものである。いや本当に大したものです。
■2019.5.17 (Fri.)
体育祭の前日準備である。今年は去年よりも生徒に関わらせているので、テントは増えたがだいぶ楽。ありがたや。
■2019.5.16 (Thu.)
体育祭に修学旅行なところに顧問会が飛び込んできてもう死にそう。
■2019.5.15 (Wed.)
体育祭の予行なのであった。毎度おなじみ道具の出し入れの確認。やはり神経を使うので疲れた。
■2019.5.14 (Tue.)
「先生髪切った?」などと愚かなことを訊いてくる生徒がいる。まるでセンスのない愚問であるなあと。
髪が短くなって現れたら、切っていて当たり前である。そうでなけりゃ病気だ。何わかりきったこと訊いてんだと。
そしてどんな答えを期待しているんだと。「切った」と答えれば満足か。それでお前は何を新たに知ろうというのか。
だから「先生髪切った?」と訊かれるたび、面倒くさい思いを抱えて「お前は気が利かねえなあ!」と返すことになる。
「切ったに決まってんだろ、でなけりゃ病気だ。『先生髪切ったんですね、かっこいいですね』まで言って100点だ」
聞くところによると、女性には「髪切った?」という質問が通用するらしいですね。女ってのはわからねえ。
■2019.5.13 (Mon.)
メンタルが弱っていると疲れもひとしおである。体育祭の準備と授業の準備と「次」へのステップと、
切り替えなくちゃいけないことが多くてよけいにすり減っている気がする。歯を食いしばって耐えるしかない。
■2019.5.12 (Sun.)
正式に願書を出すつもりだったのに、書類を確認したら特別選考の条件を満たしていないことが発覚。
結局、当初の目論見は崩れて二択を迫られることになってしまった。いやあ、これは本当に困った。
午前中はそのまま、気分転換も兼ねてレンタサイクルで御守頂戴の補完作業。
住宅地に苦しみながらもどうにか目的は達成できた。それにしても、うーん……すっきりしない。
◇
モヤモヤしながら湘南新宿ラインに揺られて平塚まで。今月のサッカー観戦は湘南×大分なのだ。
実はこれ、かなり楽しみにしていたカードである。というのも、大分はJ2から昇格したばかりであるにもかかわらず、
なんと現在3位につけているから。片野坂監督は今、Jリーグで最も注目を集めている監督と言っていいだろう。
昨季のJ2で大分は変幻自在の攻撃サッカーを展開していたそうで、それをJ1向けにアレンジしながら上位をキープ。
いったいどんなサッカーが見られるのか、楽しみでたまらない。大いに興奮しながらキックオフを待つのであった。



L: 夜道を歩いていても絶対に安全そうな恰好の片野坂監督。守備のピンチ時には別のコーチが出てきて指示を出すのも独特。
C: GK高木(右端)が最終ラインのDFに混じってボールをつなぐ。低い位置で人数をかけてビルドアップして相手をおびき出す?
R: 湘南の攻撃に対し、大分は囲んできっちりパスコースを消す。このような守備での丁寧さがかなり目立っていた。
試合が始まると、大分OBでもある梅崎を中心にして湘南がガンガン攻め込む展開に。しかし大分はよく粘る。
人数をしっかりかけて、前を向かせない守備を徹底する。そしてパスもシュートもコースを切るのが非常に上手い。
そうして引っかかったところで大分がボールを持つと、あえて低い位置からつないで対抗し、サイドへ入り込む。
湘南はハイプレスでショートカウンターを狙いたいが、大分はGK高木を含めたディフェンスラインがよくいなし、
プレスをかけようと前に出た湘南の背後にできるスペースへとボールを出していく。湘南が押しているように見えるが、
実際のところは互角だろう。むしろ湘南の攻撃を防ぎきっている分だけ、大分のペースなのかもしれないと思う。



L: 大分は前線の選手も簡単にボールを入れさせない守備をする。人数をかけて、前を向かせない守備を徹底していた。
C: GK高木が落ち着いてボールを処理するのが印象的。ディフェンスラインの下、「フルバック」といった感じのプレーぶり。
R: ディフェンスがGKも含めてボールをつないでじっくり上がる。湘南がプレスで食いついた後ろのスペースを狙っている。
大分はショートパスを回して食らいつかせようとする攻撃で、ボールを持った「強者のカウンター」をやっている感じ。
いつでも電撃的に攻められるブラジルなどが相手にボールを持たせるのが「強者のカウンター」(→2014.7.5/2015.5.3)。
でも大分はボールを持ってそれをやっている印象。冷静に考えるとそれっていわゆる「ポゼッション」なのだが、
湘南はプレスの勢いがあるので、ボールの保持と能動/受動の関係性が逆転して「強者のカウンター」に見えるのだ。
大分はハイプレスに対して低い位置でGKを含めたビルドアップを志向するので、ボールを持ってもカウンターに見える。
しかし大分の本当の狙いは別のところにあった。湘南DFの裏にある広大なスペースにロングパスを出してのFW藤本、だ。
後半に入って大分が攻撃を修正したとする記事も後で見たが、僕には90分を通した大分の戦略だったように思える。
地道な地上戦(ショートパス)で湘南の守備を油断させてからの空爆(藤本へのロングパス)、これが大分の狙いだ。
その一閃の切れ味たるや、凄まじいものがあった。52分、ボールを受けた藤本は湘南DFを2人かわしてシュート。
藤本はJFLでプレーした経験を持ち、J3鹿児島時代を含めて「異なるカテゴリ(J3・J2・J1)で3年連続開幕戦ゴール」、
「4カテゴリ(JFL・J3・J2・J1)で開幕戦ゴール」というとんでもない偉業を今年達成して注目を浴びた選手である。
実は2年前、僕は鹿児島で藤本のプレーを観たのだが、いかにもFWらしいギラギラした姿が印象的だった(→2017.8.19)。
今日もその実力をはっきりと見ることができた。また、藤本のために隙をつくるFWオナイウの運動量も賞賛すべきだ。
能力の高い選手たちが自己の判断を積み重ねてプレーしているのではなく、チーム全体がプランを共有して戦っている。
もし湘南が引いたら引いたで、おそらく大分にはBプランがあったはずだ。そういう凄みを感じさせる戦いぶりなのだ。


L: 一瞬の切れ味で決勝点を決めた藤本(左から2人目)。大分の本当の狙いは、彼へのロングパスだったのだ。
R: 惜しいシュートを放つオナイウ。身体能力が高いうえに献身的に広範囲を走る。藤本との2トップは魅力たっぷり。
大分のプレーを見ていると、ひとつひとつのプレーに意図を感じる。サイドへ侵入するためのショートパスはその典型。
いちばん印象的だったのは、パントやロブによる時間の使い方だ。滞空時間の長いボールをうまく活用することで、
自分たちのポジションを修正する時間をつくっている。この戦い方を徹底していると感じさせるチームは初めて見た。
まあここまで書いてきた内容は「片野坂監督が最高レヴェルの戦術家だった場合」を想定してのベタ褒めではあるが、
大分の意思統一のとれた迷いのないプレーぶりを見ていると、けっこう当たっているんじゃないかって気がする。
湘南だって決して悪くないプレーをしているのだが、終わってみれば「大分の手のひらの中」って感触しかしない。
僕は勝手に、選手のレヴェルが少し落ちるJ2は戦術家たちがしのぎを削る「監督次第のリーグ」であるのに対し、
J1は選手の能力が高い分だけ監督の差が出にくい「選手次第のリーグ」、そう思っていた。しかしその印象は変わった。
用兵術でJ1に旋風を巻き起こしている片野坂監督率いる大分トリニータ、どこまで行くかじっくり見させてもらおう。
■2019.5.11 (Sat.)
午前中の部活が終わると、いよいよ個人としてやるべき作業に集中する。「次」に向けての書類を書くのだ。
まず箇条書きの形で骨組みを用意して、それをブレインストーミング式に肉付けする。それから字数に合わせて削る。
油断しないように気をつけつつも、なんだかんだで慣れたもんだなあと自分で思いながら作業をしていく。
この原点をきちんと振り返る作業をやっておくこと、譲れない核の部分の言語化を経験することが大事なのである。
それは非常に疲れることなので踏み出すには決意が必要だが、いざ始めてしまえば自動的に集中できるのが面白い。
誰かに習ったわけではないが、この手順を任意の枠内で自在にやりきれる力は誇れるかもしれないな、と思う。
■2019.5.10 (Fri.)
毎シーズン恒例のPTA歓送迎会なのであった。本当に忙しい状況だが、出なくちゃいけないので出席。
とはいえ生徒たちは3年生になって以来、やる気が高まっている非常にいい状態がずっと続いているので、
保護者のみなさまに向けて存分に褒めることができる点はありがたい。思ったよりも話が弾んでよかったよかった。
■2019.5.9 (Thu.)
このクソ忙しい状況なのに、午後に研究会で出かけることに。僕はその仕事を一手に引き受けているので早めにお出かけ。
逆を言うと、今日の午後は合法的に忙しい状況から解放されざるをえないということでもある。思わずニヤけつつ出発。
予定どおりに会場の学校に着くと、ボケーッとみなさんの到着を待つ。その間、他校の先生方とご挨拶なんかしたり。
会が始まったら始まったでいつもの流れ。話を聞いて、移動して話を聞いて、また移動して話を聞いて、仕事は終了。
話の早い区は助かるなあと思いつつ街へと繰り出すのであった。全力でリラックスしてやったぜ。
■2019.5.8 (Wed.)
体育祭の準備と修学旅行の準備が同時並行する状況はマジでヤバいですぜ。
ただでさえ授業のコマ数が増えて自由に作業のできる空き時間がないというのに、仕事が際限なく襲ってくる。
今までだったら簡単に優先順位をつけてこなしていけたのに、どれも優先順位が高くて差がつけられない。
そうなったら気分の問題だが、空き時間がなさすぎて気分が乗らない。集中力を自在に操るのって本当に疲れるのよ。
そんなわけで、何がなんだかよくわからないうちに時間と仕事が進んでいく感じ。コントロールできている感覚がない。
■2019.5.7 (Tue.)
GW明けでボケている間もなく体育祭練習がスタート。有無を言わさず切り替えさせられる感じだ。
3年生はムカデ競走が恒例となっているので練習の様子を見ていたのだが、前任校と比べるとたいへんイマイチ。
まああっちは全校を巻き込んでいるせいで異様に殺気立っているムカデで、それだけ速くて当たり前だったが、
それにしてもこちらは要領の悪さがとっても気になる。生徒たちにリズム感がまるでないのである。
実際に走るよりもまず、お互いにリズムを揃える練習が必要なんじゃないかって段階。競技として成立するんかな?
■2019.5.6 (Mon.)
小田原にて説明会。GW中に県職員の皆様はお疲れ様です、と思いつつ説明を聞いて、気持ちを新たにする。
■2019.5.5 (Sun.)
練習試合。部員たちはよくやっているけど、コーチなしでどこまで戦えるものなのかという疑問も正直ある。
コーチを頼るのはいいけど、それで試合中に選手が自分の判断に自信が持てなくなるのはよろしくない。
外から見ているわれわれよりもピッチ内の判断の方が適切なことはいくらでもある。そのバランスがどうにも不安。
■2019.5.4 (Sat.)
東京に戻ってくる。部活に旅行に打ち合わせにと、中身の濃いGWである。最終日には説明会もあるし。
まあ充実しているってことだと思っておこう。自分でもいろんな方向によく動きまわっていると思う。
■2019.5.3 (Fri.)
本日はバヒさんと作戦会議なのだ。今年の夏休みになんとかして2回目の富士登山をやろうというわけ。
前回(→2013.8.6/2013.8.7)は静岡側の富士宮口だったので、今度は山梨側の吉田口で行こうじゃないかと。
なるべく空いてそうな日ということで、8月下旬の平日に決行することにした。御守をもらいまくるもんね!
夜はバヒさんオススメの店で飲む。酒をいろいろ取り揃えているというジンギスカン屋に行ってみた。
僕も以前と比べればそれなりに酒というものに慣れているので、ご相伴にあずかってちびちびといただく。
ふだん独りでは絶対に行かない店で酒をいただくというのは、何よりもまず勉強になって楽しいのである。
バヒさん毎回ありがとうね。
■2019.5.2 (Thu.)
旅行3日目、ようやく晴れた。今日はできる限り愛知の市役所をつぶすのだ。もう純粋に市役所目的で動く。
まず最初に訪れたのは、稲沢市。名古屋のベッドタウンであり、申し訳ないがあまり存在感を感じない市だが、
市役所はモダニズム建築としてわりと知られている。国府宮駅から2.5kmほど西にあり、バスで市役所へ。
稲沢市役所は1970年の竣工で、設計は設計事務所ゲンプラン(満野久)。どちらかというと役所よりはホールの印象で、
有名どころでは前川國男の東京文化会館(→2010.9.4)や丹下健三の今治市民会館(→2015.5.6)、
また同じ愛知なら日建設計の春日井市民会館(→2018.8.13)、ああいった系統につながる感触である。
しかし明らかにスケールは1960年代のそれより一回り大きく、 1970年代の価値観として興味深い建築だ。



L: 北西から見た稲沢市役所。県道65号に面しており、辺りはしっかり郊外社会となっている。
C: 県道を挟んで眺める。規模が大きい建物である。 R: 北東から見たところ。



L: 敷地の東側は広大な駐車場。愛知県は車社会だなあ。立地が立地だからなあ。側面も実にモダニズムである。
C: まわり込んで南東から見たところ。 R: 南側から見た背面。右手前のオープンスペースにはソーラーパネル。



L: 背面側にくっついている第1分庁舎。 C: 南西から見た第1分庁舎。 R: 南西から見た本体。



L: 近づいてみる。たいへん豪快なピロティ。 C: 西から見た側面。天井の格子は建物の内部にも続いているようだ。
R: 手前にある池を縄張りにしているのか、カルガモが通り抜けるのであった。のどかでいいですなあ。



L: 台形の円柱の中を覗き込むと、食堂になっていた。 R: 北西から側面を見たところ。 R: 北西端。



L: エントランス。 C: 北東側。正面側の方が地味である。 R: 北東端。
本日は国民の休日ということで中に入れなかったが、中もファサードに負けず劣らずしっかりモダニズムだそうで、
機会があれば見たいところだ。しかし個人的には本体と同じくらい面白かったのが、駐車場を挟んだ東側の建物である。
労働組合が入っているようだが、マッシヴな本体とは対照的にスマートなつくり。でもモダニズムの遊び心が満載だ。
本体は1970年竣工だが、感じとしてはそれより少し前の、高度経済成長真っ只中の感触がする。僕はこっちの方が好き。



L: 北西から見た稲沢市職員労働組合事務所。これが正式名称かは知らないが、市役所本体以上に注目したい建物なのであった。
C: 南西から見たところ。 R: 近づいてみる。「稲沢市職員労働組合」の看板が掛かっている。うーん、秘密基地感。



L: 真横から見るとこうなっている。昭和の夢ですなあ。 C: 東側から見たところ。 R: モダニズムが炸裂している。



L: 駐車場部分にお邪魔してみた。 C,R: 北側には第3分庁舎が接続するが、あくまで職員労働組合事務所とは別の扱いみたい。
市役所本体もいいが、それ以上に職員労働組合事務所・第3分庁舎がたいへん面白かった。ああいう建築には憧れる。
余韻に浸りながらバスに揺られて国府宮駅に戻ると、今度は東側に出る。そちらには長い長い土の参道が延びており、
まっすぐ北上すること250mちょっとで立派な楼門がお出迎えである。国府宮こと尾張大國霊神社に参拝するのだ。



L: 尾張大國霊神社の参道入口。今でもこれだけ長い参道がしっかりと残っているのが偉い。 C,R: 参道を行く。



L: 尾張大國霊神社の楼門。室町時代初期の築だそうで、国指定重要文化財となっている。中の提灯には「国府宮」の文字。
C: 愛知県の神社らしく、しっかり蕃塀があってから拝殿。 R: 拝殿も国指定重要文化財だが、こちらは江戸時代初期の築。



L: 拝殿の後ろ、祭文殿があって本殿と並んでいるのがわかる。これまた独特の尾張造である。それにしても複雑な構造だ。
C: 紅白のなおいぎれ。漢字では「儺追布」と書く。厄除けの御守で、1年間持っていたものをこのように返却するスタイル。
R: 境内の西にある大鳥居。尾張国総社だけあって、一宮の真清田神社に負けないさすがの風格を感じさせる神社だった。
総社の参拝を終えると今度は一宮、というわけではないが、一宮市へ。おととい参拝しているので真清田神社はスルーし、
一宮市役所を目指す。裏で旧庁舎を解体しているところは撮ったが天気が悪かったので(→2014.8.8)、リヴェンジだ。


L: やはり撮らずにはいられない一宮駅。 R: 正面から見たところ。いいランドマークになっている。
すぐに一宮市役所に到着。石本建築事務所名古屋支所の設計で、2014年に竣工。きれいではあるのだが、
東京の港区辺りにあるオフィスビルと何ら変わらない建物である。一宮駅と比べても面白みがないなあ。



L: ぎんざ通りのロータリーから眺める一宮市役所。 C: 商店街に突如現れる一宮市役所。 R: 南東から見たところ。



L: 近づいてみる。 C: 北東から見たところ。 R: 北から見たところ。港区辺りのビルと変わらん。



L: 北西から見上げる。 C: 西側には駐車場。 R: 距離をとって眺める。うーん、おしまい。
 中もふつうにオフィスビルって感じである。
中もふつうにオフィスビルって感じである。
一宮の市街地という立地は変わらないままで14階建てになっているので、とにかく撮りづらかった。
帰りに旧名古屋銀行一宮支店でかつて一宮市役所の西分庁舎として使われていたオリナス一宮に寄ってみるが、
相変わらず建物としてはっきりせず、モヤモヤ感が残るばかり。一宮は建物の見せ方にあまり興味がない街なのか。
 オリナス一宮。鈴木禎次の設計で1924(大正13)年に竣工。
オリナス一宮。鈴木禎次の設計で1924(大正13)年に竣工。
一宮からは東の江南駅に向かうが、名古屋まで戻るのは面倒なのでバスを利用する。名鉄もいろいろ面倒くさいなあ。
江南駅からしばらく南へ歩くと江南市役所に到着。昭和の大合併で生まれた市で、「江南」とは無個性な名前だと思う。
「江」とは木曽川を揚子江に見立ててのことで、まあ確かにデカいけど、それを言ったら尾張の平野はみんな江南だ。
大雑把な名前で歴史ある地名が掻き消されてしまっただけ、に思えてならない。まあ地元がよけりゃそれでいいけど。



L: 西側の歩道橋から見た江南市役所。 C: こちらが西玄関。耐震補強ががっちりなされている。 R: 少し南西から。



L: 南西から道路を挟んで眺める。 C: 正面から見たところ。 R: 敷地内に入って東側を中心に眺める。



L: 道路を挟んで南東から全体を見ようとしたところ。幅が広い! C: 敷地内から見たらこうなる。 R: 建物の手前に池。


L: 南玄関。 R: 中を覗き込んでみるが、特にホールということはなくただの通路という感じ。
南玄関近くの定礎を見るに、江南市役所は1975年の竣工。しかし西側だけ耐震工事をしっかりやっており、
また低層棟がくっついていることもあって、どのように増築されていったのかがつかみづらい。ネットで検索をかけたら、
各務原市が耐震補強を視察した際のデータが出てきて、それによると「西庁舎」が1962年、「東庁舎」が1975年とのこと。
なんで他市のデータでそれがわかるんだ、という疑問はさておき、西側だけ補強はやはり東西に分かれていたからなのだ。
敷地の東端には江南市防災センターが2014年に竣工している。これはつまり、建て替えは当面ないということか。



L: 敷地東端の江南市防災センター。 C: 敷地内から見たところ。 R: 背面にまわって北東側から見たところ。



L: 江南市役所全体の背面はこんな感じ。こうして見ると東西がはっきり分かれている。 C: 西側中心に見たところ。
R: 北西から見たところ。V字型の屋根が明らかに議場。1962年の竣工当時は、だいぶコンパクトだったはずだ。
さて、江南市役所の南には藤之宮神社が鎮座しており、気になったので参拝。無人なので御守は頂戴できなかったが、
それにしてはずいぶん立派だった。合併もあって土地の歴史が追いかけづらいの状況は、なんともムズムズする。



L: 藤之宮神社。 C: 蕃塀と拝殿。立派である。 R: 尾張造とすると、本殿の前なので祭文殿になるのか。
 本殿。市役所はこの先、北側となる。
本殿。市役所はこの先、北側となる。
江南駅からは素直に名鉄犬山線を南下して岩倉駅へ。お次は岩倉市役所である。愛知県は市がいっぱいだなあ。
ちなみに岩倉市は愛知県で最も面積の小さい市であり、全国でも10番目の小ささとのこと。名古屋のベッドタウンだが、
それにしても合併なしでやってきたのはすごいものだ。岩倉市役所は2002年竣工で、設計は久米設計名古屋支店。
ベッドタウンらしく周囲は住宅やマンションがぎっちりで、敷地にまったく余裕がなくって撮りづらい。



L: 岩倉市役所。まずは東側の駐車場越しに眺める。 C: 近づいて南東から撮影。 R: エントランス。横から入るのか。



L: 道路が狭くて南側から撮影できない。これが限界。 C: 南西から見たところ。 R: 西側の側面。



L: 北西から撮影。脇のマンションが映り込む狭さ。 C: 北側。ふつう南に駐車場で採光するが、旧庁舎がこっちだったのか。
R: 北東から。岩倉市役所住宅地の真ん中に建つが、北と東に駐車場を持っているからこの立地でも問題ないということか。



L: あらためてエントランスを撮影。 C: 中を覗き込んでみる。うーん、閉庁日。 R: ホール部分も心なしかコンパクト。
次は北名古屋市である。しかし困ったことに北名古屋市は分庁方式を徹底しており、東西庁舎にあまり差がない。
いちおうメインは旧西春町役場である西庁舎ということになっているようなので、まずはそちらに行ってみる。
西春駅からしばらく西へ行くと、北名古屋市役所西庁舎(西を中心に方角ばっかりで、もうワケがわからない)。
また、駅に近い南側からアプローチしたのだが、南北どちらが正面なのかも大変わかりづらい。いろいろややこしい。
とりあえず1974年の竣工だそうで、東側には2016年竣工の増築庁舎。意地でも統一した新庁舎をつくらないのか。



L: 北名古屋市役所西庁舎(旧西春町役場)。まずは南東から見たところ。 C: だいたい南側から見たところ。
R: 東側にくっついている増築庁舎。これをつくったということは、現状の分庁方式を継続する意志の強さがうかがえる。



L: 南西から全体を見たところ。 C: 北側にまわり込む。こちらが正面なのか? 南側とほぼ同じデザイン。 R: 北東から。



L: 北西から全体を見たところ。 C: 少なくとも増築庁舎は北側が正面のようだ。 R: 南東から見た増築庁舎。
現地に行ってみるととにかく「西庁舎」であることが強調されており、そうなると東庁舎がどうなっているか気になる。
ゴールデンウィークはかなり日が長くなってきている時期なので、せっかくだからと東庁舎にも行ってみることにした。
面倒くさいが1駅北に戻って徳重・名古屋芸大駅からひたすら東へと歩く。こっちも西側と同様に住宅地ではあるが、
農地がそのまま宅地化していった感触が強い。つまり、どこかなんとなく田舎の匂いがして、それはそれで落ち着く。
そんな中、周囲の住宅と比べてでっかくそびえているのが、旧師勝(しかつ)町役場の北名古屋市役所東庁舎である。
定礎によると1977年竣工。偶然か、こちらの東庁舎もさっきの西庁舎と同様に、南北似たようなデザインとなっている。



L: 北名古屋市役所東庁舎(旧師勝町役場)。 C: 敷地内に入って眺める。 R: 北西寄りで見たところ。



L: 北西、少し近づく。 C: 農地越しに眺める西側の側面。 R: 敷地に戻って南西から見たところ。



L: 南側、背面。こちらもしっかり窓をとっている。 C: 南東から。 R: 東側の側面。こっちも西と似た感じ。
旧師勝町はこの辺りを中心部と位置付けていたようで、役所の周りに公共施設を固めている感じである。
この核をつくろうという師勝の力強い意志は、西春との合併の際にも発揮されたのだろうと容易に想像できる。
外から見ると「北名古屋」とは脱力するほどにコバンザメ感の強い市名だが、西春と師勝の対等な合併だけに、
大都会・名古屋への憧れがすべてを上回って、そこが落とし所になってしまったのか。尾張の感覚も少し独特だ。



L: 東庁舎の東にある東庁舎分館。 C: 東庁舎の南西に東図書館・歴史民俗資料館。 R: 南東には総合体育館。
来た道をトボトボ戻って駅まで行くと、本日最後の市役所へ向かう。名古屋を抜けてそのままさらに南へ行き、
やってきたのは豊明市役所。これがまた面倒くさい位置にあり、前後(ぜんご)駅からも豊明駅からも均等に遠い。
幸いなことに前後駅からバスがあり、それで一気に到達。時刻は16時だが、なんとかいい感じに写真は撮れそうだ。



L: 豊明市役所。道を挟んだ駐車場のさらに奥からようやく全体を見渡せる感じ。左から新館・本館・分庁舎となる。
C: 西側の本館と、その奥の分庁舎を見たところ。 R: 角度を変えて北西から見たところ。2つ顔がある感じね。
豊明市役所は増築によってかなり幅が広い集合体となっている。これだけでも十分ややこしいのに、
定礎には「定礎」とだけしか彫られていなかった。とりあえず、西側の本館が1972年の竣工であり、
格子状のファサードはかなり大掛かりな耐震補強の結果のようだ。なお、設計者は浦野設計(浦野三男)。



L: 西から見た側面。左が本館、右が分庁舎。 C: 本館メインで見てみる。まずは新館との接合部分。右が本館。
R: 敷地内で本館を正面から見たところ。竣工当時がどんな姿をしていたのかは、ちょっとわからない感じだなあ。



L: 本館に近づいてみたところ。 C: 南西にくっついている分庁舎。 R: こちらは西から見た分庁舎の側面。
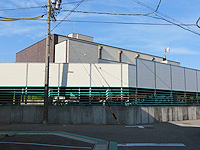


L: 裏にまわり込む。 C: 分庁舎と本館の背面。南から見たところ。 R: 南東は公園。木々の裏には新館がある。
東側の新館は2004年の竣工で、こちらの設計者は中建設計。本館の耐震工事完了は2015年度とのことなので、
増築はそれより前ということになる。新館のファサードに本館と統一性がまったくないのは、それもあるのかな。



L: 南東から見た新館。 C: 東の方にまわり込む。 R: あらためて向かいの駐車場から全体を眺める。一周完了。
以上でタイムアップ。一日で6市役所7庁舎というのは、なかなか記録的な事態である。市の集まる愛知県ならではか。
名古屋に戻るとバスで飯田へ。明日はバヒさんと打ち合わせなのだ。いったん実家で羽を休めるのであった。
■2019.5.1 (Wed.)
今日は令和最初の日である。そして私は旅行である。名古屋駅でまたも雨に降られて絶望感に苛まれている。
いや、もう、どうしたものか。昨日は飛騨一宮水無神社まで行ってしまったが、それなら今日はもう、伊勢神宮だ!
雨だけど青空フリーパスでお得に神宮参拝してやる! 御守と御札を頂戴して高校へのコンバートを全力で祈願してやる!
というわけで、名古屋駅からやっぱり3時間かけて伊勢市駅へ。きちんと外宮から参拝するぜと行ってみたら、大行列。
今まで見たことのない大行列に唖然とするが、これは御朱印を頂戴しようという参拝客の列なのであった。
令和最初の日付を伊勢神宮の御朱印で!ということのようで。申し訳ないけど僕にはまったく価値を見出せない。
ただただ、そういう欲望を持つ人々がこれだけいるのか、と圧倒されるばかりである。まあがんばってください。



L,C: 外宮の大行列。そんなに令和最初の日付が欲しいのか。理解できねえ。 R: 当方はふつうに参拝。
お参りして御守とお札を頂戴すると、バスで内宮へと向かう。が、途中の猿田彦神社前で下車して参拝。
前回は写真1枚だったので(→2012.3.31)あらためて撮影しようとする。しかし人が多くてうまくいかないのであった。



L: 猿田彦神社。参拝客でごった返している。みんなそんなに令和最初の日付で御朱印が欲しいのか。 C: 拝殿。 R: 本殿。
 境内社の佐瑠女神社。こちらも行列である。
境内社の佐瑠女神社。こちらも行列である。
ではいよいよ内宮だ。……が。まあわかっちゃいたけどね。わかっちゃいたけど、とんでもねえ人出である。
外宮よりさらに凄まじいことになっていた。今日の日付で外宮と内宮両方の御朱印を頂戴するのは難しかったみたいね。



L: 内宮前。もともと参拝客の多い箇所だが、それにしてもとんでもない行列だ。右がふつうの参拝、左が御朱印の列。
C: それでも五十鈴川は静かに流れるのであった。 R: 境内にて。いやあ、御朱印の行列は果てが見えませんな。
 内宮の参拝客。こんなん笑うしかねえぜ。
内宮の参拝客。こんなん笑うしかねえぜ。
そのまま往復してもつまらないので、今回はちょっと遠回りして戻る。本殿隣の古殿地をまわって行くと、
本殿の屋根が見えた。古式ゆかしい神明造。式年遷宮が始まった1300年前からずっとこんな光景なのだろう。



L: 古殿地にて。式年遷宮のたびに本殿が往復するわけである。 C: 雨のせいもあって厳かな雰囲気である。
R: まわり込むと古殿地越しに本殿の屋根が見えた。日本における聖性の頂点はこの光景なのかなと思う。
内宮でも御守とお札を頂戴し、いちおうこれで伊勢神宮祈願は完了である。さらばだ、御朱印の皆さん。
まだまだ時間的に余裕があるので、天気は悪いけど二見浦・二見興玉神社に足を延ばして御守チェックなのだ。



L: 二見興玉神社の入口。 C: 参道を行くぜ。 R: 社殿が見えてきた。こちらも大賑わいなのであった。



L: 拝殿をクローズアップ。 C: 近づいて本殿を見上げる。 R: 夫婦岩。今回も雨。晴れたのは中学2年のときだけかあ。
 授与所にて。夫婦守も御朱印帳も青海波の夫婦岩デザイン。
授与所にて。夫婦守も御朱印帳も青海波の夫婦岩デザイン。
せっかくなので志摩国一宮の伊雑宮にも参拝することに。となると、鳥羽駅でメシを食っておくのだ。
近鉄側の鳥羽駅には「メルヘン」という喫茶コーナーがあり、ここでおいしい「あおさうどん」が食べられるのだ。
他愛ないうどんが、地元名産のアオサのおかげで特別な味になるのが面白い。風味が本当によくってオススメである。
 「メルヘン」のあおさうどん。鳥羽に来るとこれを食べるのが楽しみになっている。
「メルヘン」のあおさうどん。鳥羽に来るとこれを食べるのが楽しみになっている。
上之郷で下車して伊雑宮へ。前回はちょうど遷宮のタイミングだったが(→2014.11.9)、いい感じに古びてきていた。
伊勢神宮と比べればもちろん小規模だが、やはり端正な聖地の雰囲気が共通していて心地よい。好きな空間である。



L: 伊雑宮の入口。毎度おなじみですな。 C: 社殿と社叢。 R: 授与所脇の木がなかなかすごいことになっていた。
参拝を終えると鳥羽駅に戻り、少し北に行ったところにある温泉旅館で日帰り入浴。雨で消化不良感があったが、
ここで思う存分温泉に浸かったおかげでメンタル的にはだいぶプラスの状態になった。鳥羽、いいところだなあ。
2日連続の雨でプランが狂いっぱなしだが、明日は天気がよさそうなので全力で市役所めぐりをする予定。やったるでー
diary 2019.4.
diary 2019
index








駐車場の端に残る御師邸跡の塀。おかげ参りの文化(→2006.8.30)も今は昔か。




阿児町安乗に到着である。




































車窓から見た生浦(おおのうら)湾。浦村かきを養殖中で、道路沿いに店がいっぱい。






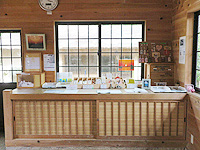











それでも鳥羽港フェリーターミナル内を撮影する性(さが)よ。


記念に撮影。3隻あるフェリーだが、今回お世話になったのは知多丸。




かわいいものである。こっちに来てくれればもっとかわいいのだが。