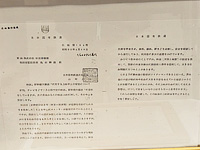diary 2024.11.
diary 2024.12.
■2024.11.29 (Fri.)
久留里線の一部廃止とか、北鉄バスの廃止・縮小が見込まれるとか、大鰐線の運行休止とか、そんなニュースばっかり。
これから行けなくなるところがどんどん増えていくなあと、たいへん悲しい気持ちになる。行けるうちに行かないと。
■2024.11.28 (Thu.)
根津美術館『百草蒔絵薬箪笥と飯塚桃葉』。館所蔵の百草蒔絵薬箪笥が国の重要文化財に指定された記念の企画。
全国から借りて集めて飯塚桃葉の総決算という内容。結論から言うと、たいへん勉強になる展覧会なのであった。
飯塚桃葉の生年は不明だが1790年没で、18世紀後半に活躍した徳島藩の蒔絵師である。藩主・蜂須賀重喜向けのほか、
交流のある他藩への贈答品をつくるなどした。初期の印籠は素朴だが、徳島藩に移ってからは飛躍的に技術が上がる印象。
明治期によくあるような「技術はすごいが趣味は悪い」(→2023.4.30/2023.5.15)にならないギリギリ感がある。
豪華だが派手ではないのだ。そこはやはり、成金趣味とは一線を画する大名の理性ということか、と思うのであった。
今回の主役である百草蒔絵薬箪笥は、とにかくやたらめったら精密。こんなことができるのかと茫然としてしまった。
まず表面全体に施された寄裂風のデザインがめちゃくちゃオシャレ。古今東西の模様が蒔絵で中和されて融合している。
いちばんの見どころはやはり裏蓋の薬草と昆虫だろうが、これが凄まじく細かいところまで丁寧に描かれている。
ただただ見惚れるしかないのであった。そして銀の合子も美しい。四角の合子は薬草で植物デザインということもあって、
インド綿製品(→2023.10.22)に通じるものも感じる。また九曜紋をモチーフにした合子もあり、大胆な発想で見事だった。
蒔絵の装飾が施された箱というとわりと一点集中というか、主題がドン!と表面に描かれているものが多い印象があるが、
百草蒔絵薬箪笥は薬草というモチーフを群像劇のように扱って、全体のバランスを品よく整えているのが素晴らしい。
なお、参考ということで緒方洪庵が実際に使っていた薬箱も展示してあり、そちらにも興奮。上手い比較だったと思う。
展示の最後には博物図譜との関連から往時の大名たちのつながりを紹介。「博物大名」と呼ばれる殿様たちがいて、
貴重な図譜を熱心に貸し借りするネットワークが存在していたのだ。 やっぱり賢い殿様はどこまでも賢いのである。
その筆頭として登場したのが古河藩主の土井利位(としつら)。こないだ古河に行った僕は大興奮である(→2024.11.4)。
雪の結晶マニアといったら中谷宇吉郎が有名だが(→2022.5.24)、ずっと昔の江戸時代に顕微鏡で雪の結晶を観察し、
それを『雪華図説』という本にまとめたのが土井利位なのだ。なおこの本は庶民の間に雪華模様ブームを巻き起こした。
利位は雪華文(さまざまな雪の結晶)をあしらった雪華蒔絵印籠を贈答品として原羊遊斎につくらせたのだが、
それも展示していて感動。何より驚いたのが家臣に宛てた書状で、雪華文を青く刷って入れていた。オシャレすぎる!
さらに漆の収納箱にまで貝殻を貼り付けまくっている、木村蒹葭堂の貝殻コレクションもたいへんなインパクト。
そして伊勢長島藩主の増山雪斎、尾張藩主の徳川慶勝の博物学的写生もすばらしい。発見の多い展覧会なのであった。
前も書いたように根津美術館にはイマイチ感があったのだが(→2024.5.6)、今回は見にきてよかったと心から思った。
それにしてもやはり、江戸時代の日本人のデザインに対する貪欲さには呆れてしまう。世界的に見ても大名から庶民まで、
こんなに熱中していた連中はそうそういないだろう。そりゃ「表徴の帝国」(→2008.11.6)なんて言われちゃいますわな。
■2024.11.27 (Wed.)
五島美術館『古裂賞玩―舶来染織がつむぐ物語』。布の世界は奥が深いので(→2023.10.22)、面白がってきた。
日本人生来のマニアックさがしっかり窺える内容。海外で織られた布についてまずこだわりが発揮されたのが、
掛軸の表具裂である。山水画などの唐物絵画をそれにふさわしい形で装飾するとなったとき、中国の布が使われた。
その需要から収集熱が拡大していったのか、江戸時代の大名たちは盛んに布の断片(裂、きれ)を集めるようになる。
そしてそれを冊子に貼り付けて「裂手鑑」をつくる。現存最古という小堀遠州の手鑑(さすがだわ……)が展示されており、
奈良時代の経錦(たてにしき)、元や明の金襴、イランのサファヴィー朝やインドのムガル朝まで押さえているそうで。
また松平不昧の手鑑もあったが、彼の編纂した本が木版色刷りで出版されていた。江戸時代の趣味人は徹底している。
意外なところでは、松平定信も集めていたとは恐れ入った。あらためて、歴史に名を残す人はやっぱり凄いと実感した。
そんな具合で仙台藩伊達家や加賀藩前田家など有力大名はみんな熱心に集めて手鑑をつくっており、元や明がワンサカ。
基本的に武家は元や明の金襴が好みのようで、公家の近衛家は植物の柄がお好きな模様。それっぽい傾向が面白い。
もうひとつの流れが茶器を包む仕覆で、茶道とともにそちらの方にもこだわりが広がっていったのがよくわかる。
これまたバラしてコレクションになっている。まあ確かにFREITAGの柄も似たようなもんだからな、と納得。
豪商の鴻池家は名物裂を分別して入れておく専用の箪笥までつくっていて、その展示に圧倒されるのであった。
個人的に興味深かったのが、中国とはまた異なるインド方面の布に対する往時の人々の関心である。
前に大倉集古館で見たが、インドは植物、特に花と蔓の曲線をリズムよく描くのですぐにわかる(→2023.10.22)。
インドの布というと彦根藩井伊家が集めていたイメージが強いのだが(東京国立博物館の展示 →2023.4.15)、
松平不昧は茶器などの木箱を包むためにインド更紗を用いていたようで、さすがの鋭さが非常に印象的だった。
また茶道との関連では、インド更紗を袱紗にする例がありたいへんオシャレ。日本人のデザインへの欲望は凄まじい。
古裂についての体系的な研究はまだまだのようだが、今回の展示ではよく目をつけて集めたものだと思う。
日本人の果てなき好奇心が確かに実感できる充実の内容なのであった。ぜひさらに詳しく知りたいジャンルですね。
■2024.11.26 (Tue.)
山中貞雄監督の遺作、『人情紙風船』を見た。みんな気をつけろ! こいつはとんでもねえ鬱映画だぞ!
『丹下左膳余話 百萬両の壺』は大傑作のコメディだったが(→2022.11.5)、『河内山宗俊』はダーク(→2022.11.6)。
そしてこの『人情紙風船』はまったく救いのない内容で、山中貞雄監督はかなりメンタルの調子が悪かったと思われる。
首吊りスタート心中ゴールとか、つらすぎる(岩浪れんじ『コーポ・ア・コーポ』はこれが元ネタだな →2024.4.18)。
どこにも逃げ場がないのは、当時の監督の精神状態を反映しているからではないか。時代に対する感性が鋭すぎたのか。
この映画をわざわざつくった理由がわからない……。ところどころにさすがの鋭さはあるが、明らかにスランプ。
封切り当時の人はそのスランプぶりに閉口したはずだ。それでもこのスランプぶりを無理やり好意的に解釈するなら、
この後に高くジャンプするためにいったんしゃがみ込んだ感じ、さらに一皮むけるための試行錯誤と受け止めるしかない。
主立った登場人物は2人いるが、きちんと紹介する段取りがなく、特徴をつかむのに時間がかかるし物語も見えづらい。
悪いんだけどこの映画を名作などと手放しに褒めている人は、物事の中身をきちんと吟味する能力がない人だと思う。
「山中貞雄」という名前だけで判断している暗愚な人だと思う。むしろこのデキを褒める方が山中貞雄に失礼だろう。
そんな映画。「紙風船が遺作とはチト、サビシイ」とのことだが、観客のオレたちゃサビシイなんてもんじゃないぜ!
■2024.11.24 (Sun.)
毎度おなじみ戸栗美術館、『古陶磁にあらわれる「人間模様」展』。
今回は陶磁器に描かれている人物画がテーマ。まずは景徳鎮を中心に、中国の子どもである唐子(からこ)の特集。
日本の場合、画題としては鶴に乗る寿老人や布袋が好まれたそうで。また「二十四孝」など物語性のあるモチーフもあり、
見る者の教養が試される世界なのであった。古伊万里でも、描かれている対象は圧倒的に中国風の人物が多い印象。
海外向けのものでは日本人もないことはないが。面白いのはオランダ人を描いたものがあることで、上客ぶりが窺える。
しかし日本の全体的な傾向としては、御所髷婦人像や歌舞伎の外郎売りなど日本人をモデルにした人形はあるのだが、
絵として人物を器に描いたものは少なめだった。この価値観の違いは気になるところである。侘び寂びなのですかな。
そして今回は人物画がテーマということで、鍋島はやっぱりぜんぜん出てこないのであった。侘び寂びなんでしょうなあ。
というわけで、人物を描いた技術は高いんだけど趣味はどうにもイマイチ、という印象の作品が多かった。
そんな僕の感覚を含め、人物をあまり描きたがらなかった日本人の感性は、かなり興味深いところである。



L:
『染付 山水文皿』。典型的な初期伊万里。 C: 柿右衛門様式の『色絵 人物舟遊文皿』。 R: 『色絵 寿老人文鉢』。



L:
『色絵 人物帆船文 蓋付碗』。 C: 半面にはオランダ人が描かれている。 R: 反対側には帆船が描かれている。
最後の第三展示室は、古伊万里の流れを勉強できる内容。もともと技術の高い景徳鎮が偉大な先輩であったが、
明から清に切り替わる混乱で景徳鎮から伊万里に技術が伝わってきたことで、作品が複雑化していくのがよくわかる。
そして中国にかわって古伊万里がヨーロッパ向けの主力となるわけだ。柿右衛門も海外受けということで発展したのね。
それにしても、戸栗美術館はとても日曜午後の渋谷とは思えない静けさがたまらないですな! 最高だぜ。
■2024.11.23 (Sat.)
平塚市美術館でやっている蕗谷虹児展が明日で終わるということで、慌てて東海道線に乗り込むのであった。
さて平塚駅に着いたら時刻は昼飯どき。確か平塚には名物があったよな、と検索すると、平塚タンメンがヒット。
駅からそこそこ近い老郷本店にお邪魔するのであった。メニューはタンメンとギョーザのみで大盛なし。


L:
老郷本店の外観。 R: タンメン。たいへんオリジナリティがあるというか、オリジナリティしかない麺。
スープは一般的な塩ラーメンよりもさらに薄い色合いで、飲んでみたらけっこうしっかり酸っぱい。
この酸っぱさが平塚タンメンとのこと。そこにどことなくソーメンみたいな麺と刻みタマネギと大量のワカメで、
オリジナリティしかない麺料理である。これは好みが分かれるのではないかなあ、と思いつついただく。
食べ終わる直前に卓上の手作り辣油を入れてみたら、見事なスーラータンメン(酸辣湯麺)となったのであった。
そこでようやく、なるほどこれはテメーで好きな辛さのスーラータンメンをつくりなさいということか、と気づく。
そうなるとスーラータンメンとギョーザで食べるのが正式な作法のように思えてきた。ま、いずれリヴェンジしましょ。
 そこそこ歩いて平塚市美術館に到着。
そこそこ歩いて平塚市美術館に到着。
では『大正・昭和のモダニスト 蕗谷虹児展』。10年前には新発田の蕗谷虹児記念館に行ったが(→2014.10.18)、
なんせ竹久夢二(→2023.6.4)と中原淳一(→2023.11.27)の間の人なので、あんまり好みというわけではない。
好みではないが、日本のカワイイ文化を分析するうえで重要な存在である。そういう社会学的な興味関心から見ていく。
蕗谷虹児記念館と弥生美術館からたっぷり作品を借りており、展示はかなり充実した内容なのであった。
作風としてはバリンボリンにアール・ヌーヴォーというかビアズリーで、1920年代モダン(→2024.4.29)のど真ん中。
10歳ほど上の高畠華宵を思わせる三白眼がやはり特徴的だが、つまりは上目遣いの女性を描いているということだ。
版画みたいなタッチのモノクロ作品をペンで描いているが、これは印刷との関係で有利にはたらいたのではないか。
なんとなくビアズリーとマンガの中間という印象で、これが手塚治虫へとつながっていったのではないか、と思う。
講談社の『世界名作童話』シリーズ、その中でも1941年の「船乗りシンドバッド」の挿絵が彼の完成形だろう。
構図も練ってあって上手いのなんの。1920年代の作品は不安定さもモダンの味ということで支持を集めた感じだが、
1930年代からいい意味でのこなれたマンガらしさが出てきて、安定感が増してくる。そして1940年代になると、
個性を消化した画家としての頂点に達した印象だ。ただこの時期は戦争の時代であり、それまでの作風が否定された。
しかしそれでむしろ生来の才能が濃縮され研ぎ澄まされたように思える。戦争関連の絵も数点あったが見事だった。
戦後はカラーで絵本を手がけるが、残念ながらモノクロのときほどの切れ味は感じられなくなってしまう。
カラーでかえって想像力をかき立てる余地が少なくなっており、個性を発揮するポイントが失われてしまっている。
僕からすると、いちばん脂が乗っていたと感じられる時期が戦争と重なってしまったのは、たいへん残念で仕方がない。
それでもしっかり評価されているから十分に偉大なのだが、本当はこんなもんじゃなかっただろう、という感触がある。
今回の展覧会ではその片鱗に触れることができたので、大いに満足である。でもやっぱり、残念さが先に来るなあ。
■2024.11.22 (Fri.)
『リュミエール!リュミエール!』。1895年にオーギュストとルイのリュミエール兄弟がシネマトグラフを発明し、
スクリーンに映像を投影した。これが一般的な映画の起源とされているが、そのフィルムをあらためて映画化した作品。
シネマトグラフの映像は1本が50秒の長さで、それを110本つないで解説のナレーションと音楽を入れている。
 ポスター画像をもらったので、いつものサイズで貼り付けてみる。
ポスター画像をもらったので、いつものサイズで貼り付けてみる。
映像が鮮明で驚いた。もちろん懸命な修復作業のおかげだろうが、それにしてもまったく苦にならないとは恐れ入った。
僕がまず興奮したのは、19世紀末の舗装されていない街並みと雑踏が味わえること。馬車はあるが自動車がない空間で、
自動車で空間の文法が書き換えられる前はどのような状態だったのか、映像として経験できることに大いに感動した。
もうひとつ印象的だったのが、映し出される人々の表情がみんな優しいことだ。未知のメディアに対する好奇心が、
かなり高い純度で記録されていると思う。発明をポジティヴなものとして受け止める純粋な視線が、実に微笑ましいのだ。
映し出されるのはすべて現実なのだという感動を追体験できる内容で、むしろ50秒という短い時間に詰め込まれることで、
現実が俳句のように研ぎ澄まされた形で記録されているように感じる。これがテンポよくつなげられて、たいへん濃密。
撮影しているのは主に弟のルイ=リュミエールだが、固定されているがすべてを見通せるようなカメラアングルで、
それこそがすべてだったのではないかと思う。映像に慣れきった現代の感覚でも何ひとつ見劣りするものがなく、
映画作家としてのルイ=リュミエールの非凡さが実感できる。むしろ彼の映像表現の完成度の高さこそが、
リュミエール兄弟を映画の発明者たらしめたのではないかと思う。つまりシネマトグラフというハードだけでなく、
映像表現というソフト面の技法が彼によって発明されたことで、初めて「映画」が意味を持ったということだ。
具体的には、遠景と近景を同時に収める、縦の動きと横の動きを対比する、そういったことにすごく敏感なのだ。
つまりただ目の前の対象を写すのではなく、ひとつの画の中に複数の意味を込める。それで50秒が何倍にも拡張される。
しかもカメラが固定されていることを逆手にとって、汽車や船に乗って視点を動かしながらの撮影もやっているのだ。
さらにはクランクをぐるぐる回して撮影している姿を撮影することまでやっていて、メタな視点までも押さえている。
映画は発明された時点から、すでに映画だったのだ。映画の可能性は、最初からトップスピードで開拓されていたのだ。
そしてこの50秒(=カット)を複数組み合わせてつなげていけば、容易に物語ができあがる。もうその直前まで来ている。
撮影されている対象も、実に幅広い。世界各地の日常を記録するだけでなく(なんと明治の日本も登場する!)、
軍隊の行進や大道芸、コメディも演じられているし、殺陣もある。飛び跳ねる猫だってきちんと記録されている。
見ていてふと、これは『加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ』の「おもしろビデオコーナー」みたいだと思った。
なるほどやっていることは100年経っても変わらないのである。つまりは経験を共有したいという欲望こそが、
人間の本質というわけなのだ。文字から映画へ。人類が新たなメディアを手にした感動を、直に味わえる時間だった。
■2024.11.21 (Thu.)
三嶋与夢/潮里潤『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』。一段落ついたようなので感想を書くのだ。
異世界転生で乙女ゲームの世界に放り込まれて聖女や悪役令嬢と仲良くなるのはこれまたテンプレなんだろうけど、
すがすがしいまでにやりきってくれたのがこの作品。たいへん楽しく読ませていただいた。アニメ化したのも納得だ。
(アニメは絵に硬さを感じたが、石田彰(→2019.12.29)のルクシオンがポジティヴに昇華した印象。妙な説得力がすげえ。)
聖女もかわいけりゃ悪役令嬢もかわいいし、王妃もよろしい。女性陣の魅力をきっちり描いているので、それでもう十分。
そしてこのマンガの偉いところは、逆ハーレム対象のポンコツ5人衆と偽聖女にも、なんだかんだで見せ場がある点だ。
キャラクターへの愛情をしっかりと感じるのである。話がテンプレだとしても、キャラが生きているので楽しめるわけだ。
また、カヴァー裏の「残念だったな」も毎回凝っていて面白い。キャラクターへの愛情が深いからこその工夫である。
さて思ったのは、「悪役令嬢(→2023.9.29)」という属性について。あくまで「悪役」というのが重要なのだ。
乙女ゲームにおいて悪役令嬢はヒロイン(聖女)に対抗するラスボスという扱いになるわけだが、ラスボスであるゆえ、
スペックが無条件に高く設定されているということだ。つまり悪役令嬢は、最初から各方面でポイントが高い女子なのだ。
また、悪が悪である理由を掘り下げることは、「悪役」への同情につながる。改善点が明示されている状態というわけだ。
そして「悪役」であることから、性格的にはツンデレであるという解釈が自然に可能となる。以上を綜合してみると、
「悪役令嬢」という属性は、大いに可能性を持った存在となる。これを物語の中心に据えるのは、なるほど合理的である。
清く正しいヒロインと、成長して「悪役」を脱する令嬢との対比。これはそれぞれ性格の異なる魅力的な女性を提示する、
ある種のテクニックとして機能するのである。ふたりを並べれば、もうそれだけで一定のドラマができあがるのだ。
アンジェとリビアで120点は異世界マンガ史に残る名シーンだと思うのであります。ふたりにぐちゃぐちゃにされたいです。
■2024.11.19 (Tue.)
東映高倉健まつり、最後を飾るのは『幸福の黄色いハンカチ』。こちらは松竹、山田洋次監督作品である。
この映画を見たことがない状態で夕張に行き、「幸福を希うやかた」に行ったことがある(→2012.6.30)。
その後、長野パルセイロの試合観戦から帰るバスの中でDVDを見て、大いに感動したのであった(→2012.10.15)。
しかしそれから12年が経過し、僕のお粗末な脳内では物語が10秒に編集されてしまっているのが実情である。
「百姓」を連発する武田鉄矢、ビールを必死で飲む健さん、青い空を背景にたくさんはためく黄色いハンカチ、
そして武田鉄矢と桃井かおりの濃厚なチュッチュチュッチュ、以上。さすがにこれはいかんので映画館でいざリヴェンジ。
 展示されていたポスター。黄色いハンカチにサインも粋である。
展示されていたポスター。黄色いハンカチにサインも粋である。
前回のログでは山田洋次監督をひたすら褒め讃えている。やはり今回も感想は同じで、最強の映画監督だと思う。
われわれ観客がよけいなことを考えず楽しめるようにする、その目的に対して恐ろしいほど細心の注意を払っている。
そうして大衆向けの娯楽という枠にさりげなく収めているんだけど、やっていることはものすごく高度なのだ。
その凄みを感じさせないのがまた凄いのである。たとえばカメラアングル。われわれは自然に受け入れてしまうが、
実は誰もがすべてを理解できるように撮っている。山田洋次の辞書には「説明不足」という言葉がまったくないのだ。
美しい画を撮るのではなく、誰もがわかる画を撮ることだけに集中している。「見ただけでわかる」という恐ろしさ。
話の流れもまた無駄がない。この物語は端的に言うと、「男が成長して女に認めてもらう話」である。
それを二重構造にしているのが凄い。まずロードムーヴィーという、経験と成長を前提とする骨組みを用意する。
そこに若い男・中年の男・女という、わずか3種類の異質さをぶつけるミニマルな構成が、ものすごく巧みなのである。
鴻上尚史『トランス』(→2003.5.26/2005.11.10)に通じるミニマルさだが、それで十分にドラマをつくりあげてみせる。
まったくの他者が、同じ空間を共有しているうちに関係性を構築していく。ミニマルなだけに、濃密に変化/成長する。
まず前半は徹底してコミカルな武田鉄矢を描き、オトナな健さんとの差をつけておく。説教もするシーンが実に巧い。
しかし後半は謎解きとともに健さんの弱さを一気に出していく。男のみっともなさをあらかた詰め込む見事な構成だ。
そして健さんは弱気になるも過去と向き合い、奥さんに認めてもらう。凄いのはこのやりとりを遠景で撮ったことで、
2人がもはや誰にも関与されない領域にあると示しているのである。またこのできごとを通して武田鉄矢も成長し、
最後に桃井かおりから認められる。ここでどことなく軽い感触に戻して終わるのも、一般性を持たせていて鋭いのだ。
健さんの重たさと武田鉄矢&桃井かおりの軽さを等価に扱っているのが、人間としての真理を突いているのである。
それは一見軽くても、きちんと重さというか2人にしかわからない絆があるかもしれない、という公平さでもある。
そしてこのことは、物語が娯楽として終わることにもなっている。もう何から何まで巧さしかないのだ。
物語が演じられる舞台空間も秀逸で、『トランス』では椅子2脚だったが、こちらの武器は真っ赤なファミリア。
車という、閉鎖していて適度に密な距離感になる空間、 その特性を生かしきっていることも、またとんでもなく巧い。
基本的には武田鉄矢が運転席、桃井かおりが助手席、健さんが後部座席に陣取る。実はトラブルが起きるのは、
武田鉄矢以外の2人が運転しているときに限られる。つまり武田鉄矢は物語を前に進めるドライヴァーなのである。
車を降りるとトリックスターだが、ここは徹底している。逆に鉄矢以外がハンドルを握ると、トリックスターに変身する。
そうして物語は進んだりトラブルに見舞われたり、ロードムーヴィーが展開されていく。そして経験と成長が描かれる。
助手席に座る桃井かおりは男を認める役割を課せられた女で、物語を導いていくナヴィゲーターとなっている。
後部座席の健さんは、観客とともに奥さんの元へとただ運ばれていく。実はきちんと役割が座席に反映されている。
山田監督は絶対にこの関係性をわかったうえで、3人をそれぞれの席に座らせている。恐ろしく緻密にできているのだ。
武田鉄矢は責任を持って健さんを届けるという任務を果たして成長する。そうして桃井かおりとのゴールに至るわけだ。
以上、作劇の観点からも、ものすごく完成度が高い。この手腕を見せつけられると、山田監督が「最強」となるわけで。
さて僕にとっては今作が高倉健まつりの最後ということで、「高倉健」という俳優についてあらためて書いておく。
とは言っても基本的には前に書いたとおり(→2024.11.12)。どうしても当て書きになってしまう俳優だなあと思う。
むしろ健さんの揺るぎないイメージがまずあって、そこにスタッフがどうストーリーをハメるかの勝負になっている。
信頼と実績の健さん。背の高さと姿勢の良さが大きな武器になっており、ウルトラ猫背の僕としてはただただ羨ましい。
凄いのは、その武器を生かしながら観客の代弁者をやりきった存在感である。まあ、それがスターってことですなあ。
9作品ともたいへん勉強になったし、純粋に物語として楽しませてもらった。いやぁ、映画って本当にいいもんですね。
 高倉健まつりのたびに必ず有楽町駅のC&Cカレーを食っていた。食い納め。
高倉健まつりのたびに必ず有楽町駅のC&Cカレーを食っていた。食い納め。
機会があればぜひ、ほかの健さん映画も観たいものである。やっぱり映画館で観るのは特別感があってたまりませんな!
■2024.11.18 (Mon.)
東映高倉健まつり、『新幹線大爆破』。前にリョーシさん家のTVで一瞬だけ見て、それで存在を覚えておりまして。
今回の高倉健特集では、僕の中では最優先の鑑賞対象だったのである。評価が真っ二つに割れている伝説の映画。
結論から言うと、この作品は「日本映画史上、最高傑作のひとつ」と見なしてよいと思う。順位は好みの問題だが、
トップグループに位置しているのは間違いない。この映画の価値がわからない人が本当にかわいそう、ってくらい。
問題はやはり152分という長さで、これが大コケの主要因であろう。海外では100分版と115分版で爆発的にヒットした。
ただ、これは作り手からすると絶対に削れないのもわかる。究極的には「削るのも腕」なのだが、カットではなく短縮、
やるとしたら犯人側の事情をテンポよく縮めるしかないと個人的には考える。それくらい内容の密度が高いのである。
正直なところ客も全員賢いわけではないから(特に東映の俗っぽさを求める層)、意地で2時間に縮めたものを公開して、
後からディレクターズカット完全版という二段構えなら絶対に大成功したのに、と思う。それだけの価値がある傑作だ。
この映画がいかにとんでもないことをやっているかは、「新幹線が時速80km以下になると爆発する」というプロットを、
あの時代に考えついたということだけでもわかるはずだ。まずそもそも、この発想が出てくること自体が異常なのだ。
その斬新すぎる設定に、クライムサスペンスでパニックムーヴィーで人情ドラマでお仕事ものの群像劇でハードボイルドで、
風刺までしっかり入れてある。学生運動の名残は今となっては古いが、テロで決断を迫られるのは今も何ら変わらない。
つまりは本質を衝いているのだ。これだけの要素を破綻なく詰め込んでみせた手腕には、ただただ畏敬の念しかない。
どのジャンルでも骨太な仕上がりで、演技も舞台装置もとことん丁寧。音楽もスカパラにカヴァーしてほしいスパイ風味。
まあその分、盛りだくさんすぎるのも事実で、あまりにも完成度が高いために削れなくなってしまったことは否めない。
とはいえクリエイター気質の人なら、恐ろしく高いレヴェルで提示される物語に、間違いなく衝撃を受けるはずである。
僕にはもう、何もかもたまらない面白さだった。「こんなことができるのか!」の連続で、152分間感動しっ放し。
でもどれだけ凄いことをやっているかわからないお客さん気質の人は、「長い」の一言で片付けてしまうだろう。
そりゃ粗を探せばいろいろある。柔道部員と火事はさすがに改善の余地がある。また胎児の命が失われたことに対して、
もう少し動揺を見せてもよかったのではないかと思う。でもその些末な部分にこだわり価値を見落とすのは愚かなことだ。
ゼロからつくってここまで内容を高めることができるのか。そういう視点に立てば、この映画は最高の傑作となるはずだ。
完成度の高すぎるものを見せつけられて、かえって観客たちはあれこれワガママを言いたくなってしまうのかもしれない。
前に書いたように(→2024.11.12)、「高倉健」とは運の悪さに翻弄され理不尽の中でもがく一般大衆の代弁者であり、
高度経済成長の光と闇を一手に引き受けていたスターであることがわかってきた。そんな健さんが悪役を演じることが、
この映画ではまた抜群に効いているのだ。それが152分という長さにつながってしまっているのも事実ではあるが、
健さんの存在感がこの作品の面白さを最高レヴェルにしているのもまた確かで、あらためてその魅力を実感させられた。
というわけでここまで全力で褒めちぎってきたが、もうこれ以上同じことを繰り返してもしょうがないだろう。
とにかく観てもらえればわかる。わからなけりゃ残念。でもまあ、賢い人なら絶対にその凄さに圧倒されるはずだ。
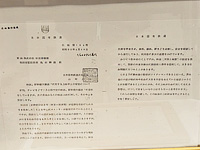

L: ロビーに展示されていた国鉄からの上映中止要望書。そんなの送っても、東映にしてみりゃ最高の宣伝材料でしかないよ。
R: 東映からの回答書も展示。「映画の持つ文化性と観客の理解度は、御想像のような低次元のものでは決してない」と。


L: 時系列を追ったポスターがあるとは面白い。この映画、つくっていて楽しかっただろうなあと思う。
R: フランス語版が凱旋公開されたときのポスターもあった。日本よりも海外の評価が圧倒的に高いのは残念。
あらためて、凄まじく面白い映画だった。「映画でできること」が極限まで詰め込まれすぎている作品だと断言できる。
■2024.11.17 (Sun.)
東映高倉健まつり、『緋牡丹博徒』。主演は藤(富司)純子で、健さんは特別出演。まあ準主役ですな。
健さんの任侠映画は『山口組三代目』(→2024.11.8)に続いて2回目だが(完全なフィクションとしては初だ)、
素直に楽しむことができた。先の展開は読めないけど、起きたことはわかりやすい。だからすっきり次へと進める。
登場人物も内面までしっかり描いている。話の筋が実に適度な複雑さで、娯楽として絶妙な線を衝いていると思う。
時代劇よりも芝居がかったやりとりが多いと感じるが、それがかっちりハマっているのが任侠映画の特徴だろう。
セリフと間がゆったりで、これが日本語らしいダイアローグなのかもと思う。まじめに考えると奥が深そうだ。
基本的にはやはり藤純子を味わう映画である。新たな路線を開拓すべく女性が主人公の任侠映画にしたのだろうが、
女性の強さがしっかり表現されているし、女性の魅力に応えて支える男たちの立ち位置のバランスもすばらしい。
きちんと見たことはないけど、夏目雅子の『西遊記』(→2005.4.24/2020.9.16)と同じ構造の成功例であると思う。
ヒロインの魅力を最大限に引き出す一方、周りもきちんと魅力的で、全8作の人気シリーズになったのも頷ける。
健さんのポジションはこれくらいの方がいいんじゃないかとすら思う。それこそ『西遊記』の孫悟空的ポジション。
若山富三郎のカワイイ感もすごいし、山城新伍のコメディも楽しい。何よりも清川虹子がすてきだわー。
個人的には、青井阿蘇神社(→2011.8.9/2015.8.18/2023.8.5)にも興奮した。たいへん楽しませていただいた。
それにしてもタイトルがいい。艶やかさと危うさが見事に同居しているうえに、7音の響きが心地よい。
■2024.11.16 (Sat.)
東映高倉健まつり、『鉄道員(ぽっぽや)』。19年ぶりの東映映画への出演で各賞総ナメとのこと。
1999年当時の僕はモーニング娘。で芸能ネタに興味が出てきても、映画になんてぜんぜん興味がなくスルー。
ゆえに知っている事前情報としては、①広末涼子が出る、②志村けんが出る、③高倉健の演じる人が最後死ぬ、くらい。
われながらひどいものである。あ、④浅田次郎が原作。もう本当にそんな程度の予備知識でいざ開演なのであった。
コテコテである。良く言えば正統派、そうでない表現なら理屈抜きに感動させようとしてくるストーリー。
ネタバレありで究極的にひねくれたことを言うと、この話はヒロスエを死神とする悲劇(→2005.6.9)なのである。
しかしとことん優しい登場人物たちに囲まれ、健さん演じる愚直で不器用な日本人が天職を全うするという柱があり、
それが悲劇としての側面を完全に覆い隠す。悲劇を悲劇と思わせないメカニズムがしっかりと機能しているのだ。
結果、ひねくれ者でない観客たちは、なんだかよくわからないうちに「いい話だなー」と感動させられてしまうのである。
僕みたいなひねくれ者からすると、骨組みを悲劇にすることで泣かせ、肉付けをハートウォーミングにして泣かせる、
たいへん戦略的な物語ということになる。そしてそれを肯定的に認める表現が、「正統派」ということになるのだ。
僕は原作を読んだことはないが、「制服でまっすぐに立つ不器用な職人」という健さんのパブリックイメージに、
完璧にマッチする素材を見つけてきたことに素直に感心する。健さんの目線を隠す帽子もまた大きな武器になる。
これだけ理想的な設定はそうそうあるまい。面白いか面白くないかではなく、ただ全力で泣かせる。そういう作品。
それにしても全盛期のヒロスエの破壊力よ。思いだすのは大学生のとき、新宿に出かけようとしたところ、
国立駅前のさくら銀行(当時)で何やらロケが始まりそうな雰囲気。さくら銀行のCMには広末涼子が出演しており、
もしかしたらと思ってすぐにマサルに連絡を入れ、僕は新宿へ。当時のマサルはかなり熱狂的なヒロスエ好きで、
国立にやってきたマサルは生ヒロスエを堪能したのであった。そのときにマサルから一生分の感謝をされたのだが、
おかげでそれ以降の人生でマサルから感謝をされたことがない。そんなマサルの狂い方も理解できる破壊力だった。
志村けんの演技については、亡くなったことが本当にとんでもない損失だったなあと思わされるすばらしさ。
真剣な部分とコミカルな部分と最大の振り幅を披露しつつ、この映画ならではの泣かせる要素をしっかりとやりきる。
正統派な内容に木村大作のカメラ(「キャメラ」って気取り方が僕は嫌いだ)がきわめて効果的なのもまた大きい。
正直言うと、僕は木村大作の画からは「どうだ、すごいだろう」という得意げな匂いを感じるのであまり好きではないが、
先日の『駅 STATION』もそうだけど、実際すごいことはすごい。問題はそのすごさが映画本体とズレることがある点だ。
しかしこの『鉄道員(ぽっぽや)』に関しては、すべてがいい方にハマっている。そこはさすがと言わざるをえまい。
そんなわけで奇を衒うことなく正統派をやりきった降旗監督も偉い。きちんとした脚本ならきちんとできるんだな。
まあいちばん面白かったのは、健さんと稔侍のBLでもあるという先進性ですな。稔侍がどこまで本気だったのか。
■2024.11.15 (Fri.)
本日は一斉研究授業の日で、当方は昨年やったので今年は気楽な見学者なのであった。
しかし協議で困るたびにオレに話を振るのはやめてほしい。すっかり便利なドラえもん扱いですよ。
さすがに今日はなかなか調子が悪かった。いろいろ考えてしまうよね。
■2024.11.14 (Thu.)
詳しくは書かないけど、われわれは最大の理解者を失った。
世の中、理不尽なことが本当に起きるのだと思い知らされた。
自分にできることなんてごくごくわずかだが、できることはしますので。どうか、どうにか。
■2024.11.13 (Wed.)
東映高倉健まつり、『花と嵐とギャング』。時期的には東映任侠映画の前史、「東映ギャング路線」の嚆矢となる作品。
この手の作品は鈴木清順で宍戸錠の『殺しの烙印』を思いだすが(→2022.11.4)、こちらの方が6年も早いのであった。
石井輝男監督が東映に移籍して初めて高倉健と組んだという作品で、明らかに「いつもの健さん」とは異なる風味。
そもそも役名が「スマイリー健」ということで、もうこの時点でしっかりとコメディテイストなのである。
鶴田浩二の方がスマイリーやんけ、とツッコミを入れつつも、こういう健さんもいいなあとニヤニヤしつつ観る。
特筆すべきは石井監督のカメラワーク。俳優とカメラの双方が移動しながらの演技、効果的な顔のアップの多用、
そういった奇抜さと細やかな配慮の両立により、座席に座っていてもストレスを感じさせない視点の動きになっている。
観客に状況を理解させるわかりやすさがきちんとありつつ、それでいて(みんな悪い人なので)ストーリーが読めない。
基本的には荒唐無稽なコメディ気味で、肩肘張らずに観られる娯楽作品だが、それにしてはカットの切れ味が鋭い。
重さを極力排除した演技の健さんということもあってか、石井監督の才気がビンビンに伝わって、そっちの方が印象的。
さて本作の若い健さんを見ていると、「静」のイメージではなく、きちんと「動」という印象を受ける。
でも後年の健さんは間違いなく「静」のイメージで、本当にうまくパブリックイメージをシフトしていったのだと思う。
おそらくは「多くを語らないキャラクター」と「アクション」という相反する要素がもともと同居していた俳優で、
その反比例を生かしつつ、さまざまな映画監督と組みながら最適解のバランスに収束させていったように思える。
これまでの作品を見てきて、健さんの礼にはパターンがあることに気がついた。丁寧な礼は、まずじっと立って、
まっすぐ相手を見つめてから間を置いて、素早く頭を下げる。それに対して雑な礼は、全体の動きを止めることなく、
体が傾いた状態でサッと済ませる。この違いと「静」「動」の関係は、示唆するものがあるのではないか。
健さんの丁寧な礼のパターンが固まったことと「静」のイメージの確立は、実はつながっていると思っている。
今回の「没後10年 高倉健特集」のラインナップは、王道もあるけどわりと変化球主体であるっぽい。
『花と嵐とギャング』はその中で最も古い作品ということで(1961年)、たいへん貴重なものを見られてよかった。
それにしても清川虹子の母ちゃんの存在感よ。石井監督の顔アップで迫力がとんでもないことになっている。
■2024.11.12 (Tue.)
東映高倉健まつり、『野生の証明』。この作品は東映ではなく角川の配給。
感想としてはとにかく、「これが角川映画か!」ということ。1978年公開だが、勢いが凄まじい。
やたらと金がかかっている。そうして誰も見たことのない映像を生み出し、観客の度肝を抜きたいということか。
それも映画をつくる立派な理由ではあるが、資金力にモノを言わせる価値観は、最初期のバブルのノリであろう。
見ていてなんとなく、みやすのんき『冒険してもいい頃』はこういう時代だったんかなあ、と思うのであった。
中盤まではミステリ、後半は金の力を全開という感じ。細部は粗いが、俳優を含めた実写の力で有無を言わせない。
「絵力」とでも表現すればいいのか、現実に物をつくって動かしてしまえばそれだけで説得力が出てしまうのである。
ある意味でたいへん幸せな時代だったのだなあと思う。その点でもこの映画は貴重な記録になっているのではないか。
僕としては、そういう社会学的な興味関心と、娯楽のヴェクトルをそっち方面にどこまで伸ばせるかという挑戦、
そう受け止めて途中からは「おおー」って面白がって見たが、基本的にはツッコミ入れてナンボな仕上がりの映画だ。
「健さんで限界まで金をかけたアクションを撮りたい!」以外の動機が見つからないのである。そのためだけに全力。
軟腐病という設定も、歪んでいる世界を敵にまわすという展開も、まったくもって生かしきれずにアメリカロケに突入。
娘がただ不安定なだけではどうにもならない。そしてこの無茶な設定なら、ラストはまあそうなるわなという結末。
話としてはもうめちゃくちゃで、資金力による映像美と健さんのアクションを堪能する映画としか言いようがない。
でも正直、わーなんかすげえもん見たわって感じで、不思議とイライラ感をおぼえることなく帰路についたのであった。
『野生の証明』はアクション健さんの集大成という位置づけだと思うが、見ていて昔の人の感覚がようやくわかってきた。
なるほど健さんは、要領のいいやつなら避けられるものが避けられない、運の悪さに翻弄され理不尽の中でもがいている、
名もなき一般大衆の代弁者としてスターになったのだ。それを象徴するセリフが「自分、不器用ですから」というわけだ。
標準以上の能力を持ちながらも、あくまで弱者の側に立ち、また弱者の分をわきまえる。そこに大衆が熱狂したのだ。
健さんのポジションは、現代風に言うなら「なろう」の主人公に近いかもしれない。でも異世界ではなく現実で戦う。
そして陰を隠さず滲み出させる。戦後、そして高度経済成長の光と闇を、一手に引き受けていたのではないかと思う。
「高倉健」というスターが成立した時代、また彼が現実のものとして最後までやりきった「高倉健」という存在、
それを「昭和」という一言でまとめるのは乱暴だろうけど、「昭和」の一側面をつかむ重要な手がかりなのは確かだろう。
さてここまで丹波哲郎と田中邦衛が皆勤賞。丹波哲郎はつねに高倉健を抑えるポジションにいる印象。
田中邦衛の顔は藤子不二雄Ⓐ(→2023.2.4)のマンガ的な役割だなあと思うのであった。ンマーイ!って感じ。
機関銃を持つ前の薬師丸ひろ子は新鮮。後年『あまちゃん』の鈴鹿ひろ美になると思うと、時間ってすげえとびっくりだ。
■2024.11.11 (Mon.)
東京ディズニーシーのビッグバンドビートが終了するというニュースが飛び込んできた。
個人的にはTDSで最も好きというか、もうほぼそれしか興味がない演目なので、たいへん残念である。
とは言うものの、もうTDSに行く機会なんてないだろうし、コロナを機に生演奏じゃなくなっているというし、
初めてBBBを観た直後に買ったCD(衝動買いしたのである)を聴いていればいいや、と割り切ってもいる。
日記の過去ログで確認したところ、5打数4安打で行っていた(→2012.2.9/2012.3.8/2014.2.25/2014.3.7)。
(なお1打数はディズニー大好きな先生にくっついていたのでスルーした、やむをえないものである。→2017.3.10)
まあ4回も行っていればいいだろう。曲を聴いてあのショウを思いだし、贅沢な時間を噛み締める。それだけさ。
■2024.11.10 (Sun.)
東映高倉健まつり、『駅 STATION』。まあ東映じゃなくて東宝なのだが。こういうときの協力関係、いいですね。
一言で言うとこの映画、「巨匠の驕り」。謙虚さのない奴はたとえ巨匠と呼ばれていてもダメだ、とよくわかる例。
役者は全員やるべきことをやっていて、それで全体の雰囲気をどうにかもたせているんだけど、まあ結局は駄作である。
独りよがりな脚本を監督がまとめきれずに迷走。これを名作だと言う人は、よっぽど面白い映画を知らないのだろう。
まずタイトルの意味がわからない。そして北海道の治安悪すぎ。スタッフは最初っから話の筋がわかっているからいいが、
観客はゼロからのスタートである。でも巨匠はワガママを通すので、観客の思考を置いてけぼり。展開がとっても乱暴だ。
たぶん女性を「駅」に見立てて、そこを行き来する男を描くことで全体に群像劇っぽさを持たせたいんだろうけど、
健さんが絶対的な主軸なので群像劇になりっこないのである。結果、女性たちはただ翻弄されるだけなのであった。
この映画が本来描くべき(描きたかった?の)は、「能力を利用されて駒として扱われる男の悲哀」ではないかと思う。
まあつまりは「いつもの健さん」である。だからってただ健さんを撮るだけで、自動的にいい映画に仕上がるわけがない。
そこをまったくわかっていない巨匠が何の謙虚さもなく、いつもどおりにやればいいんだろ、と慢心している情けなさ。
観客に対する上から目線が満載で見ていて腹が立ったけど、役者の皆さんの懸命さのおかげでどうにか中和される感じ。
まずきちんとすべきは、健さんじゃなかった三上英次にとっての射撃の位置付けである。冒頭だけでは到底足りない。
そもそも選手からコーチへという立場の変化すらろくに描かないで済ませており、それで心理が伝わるはずがないのだ。
継続的に射撃に取り組むシーンを入れ、三上にとっての射撃の重みを振り返らせる。それを十分にやっておかなければ、
「何のための射撃の腕なのか」という主人公の苦悩は伝わらない。アクションシーンがかっこいいほど逆効果になる。
また、健さんは基本的にモノローグを出さない人なので、彼の心理を観客に伝えるためにはダイアローグが必要になる。
でも「自分、不器用ですから」な人だから、会話の多用を嫌がるかもしれない。それなら、周囲がしゃべればいい。
健さんはそれに対して頷くか黙るかすればいいのだ。そういう配慮をサボっている脚本のどこが優れているというのか。
本来なら物語とは送り手側が用意するもので、俳優がそれを表現し、観客に受け止めさせて共感を得させるはずなのだ。
しかしこの映画はキャラクターの造形を俳優に丸投げし、心情どころか物語の解釈すら観客に丸投げしてしまっている。
そこにあるのは巨匠の驕りに他ならない。観客を思った情報の取捨選択ができないのは、想像力の欠如。驕りである。
 やはりこのセリフなのか。
やはりこのセリフなのか。
脚本で唯一褒められるところがあるとすれば、「樺太まで聞こえるかと思ったぜ」というセリフ。オレも言ってみたい。
でもこれが実際に発せられた言葉ではなく、健さんにしては珍しい心の中の声つまりモノローグなのは、かなり示唆的だ。
自然な説明ゼリフを組む能力がないから、説明不足になる。それを健さんの背中だけで理解しろってのは乱暴すぎる。
頭のいい人がつくれば、最高級の「いつもの健さん」になったかもしれない。でも驕った巨匠にその能力はなかった。
■2024.11.8 (Fri.)
東映高倉健まつり、『山口組三代目』。親分の自伝の映画化である。実録すぎるだろ!
よくこんなのつくれたな……と呆れるしかない。昭和ってのがなかなかとんでもない時代だったのがよくわかる。
しかし映画は丁寧につくられていて、昭和初期の雰囲気がつかめる貴重な記録となっている。
みんな貧乏だったのだ。そして家族より大事な仲間というところから梁山泊的ピカレスクへと誘導していく。
盃を交わすシーンはいかにも古めかしい儀式といった仰々しさだが、あの時代なりの格好のつけ方だったのだ。
それと比べるとわれわれの行動からは重みがなくなったなあ、と思う。何もかもが軽くなっている(→2015.1.2)。
ストーリーとしては、若き日の三代目が男としての貫目を増していく姿が細かく描かれていて興味深い。
でもこれ以降、組織のリーダーとしての話になって、さらに内容が面白くなっていくはず。そこがたいへん気になる。
見ているうちに「なるほどヤクザ・任侠映画とは、昭和における西部劇なのだ」と気がついた。
前に書いたが、西部劇とは、社会からはずれた人間による、社会制度──家庭や組織、安定への挑戦である。
彼らの一瞬の栄光と、永遠の敗北が描かれる(→2005.6.30/2006.1.27)。それと基本的には同じ構造だ。
高倉健は昭和のジョン=ウェインと言えるかもしれない。観客たちは象徴としての健さんを期待していたわけだ。
映画スターが存在した時代とは、映画のヒーローと演じる俳優がごっちゃになっていた時代だったのだ。
ある意味で大衆はたいへん無邪気だったのだが、それと同時に、素直に乗っかって楽しむ賢さもあったと思う。
丹波哲郎やアラカンなど『網走番外地』の俳優がこっちにもけっこう出ていて、少々混乱した。田中邦衛は平常運転。
そして「あーこれがスターシステムか」と納得。映画会社の「専属」が重要だった時代の感触を味わうことができた。
あとは菅原文太が広能(→2006.3.27)に見えて困った。そして『太陽を盗んだ男』(→2003.11.16)で、
刑事が文太じゃないといけない理由がようやくわかった。今さらながら映画の流れを勉強させてもらっとります。
■2024.11.7 (Thu.)
没後10年ということで、東映高倉健まつりがスタートである。教養のない自分にしてみれば映画館で名作を観るチャンス。
そんなわけでここから何日かかけて、健さん主演(助演もある)映画のレヴューをいろいろと書いていくのである。
 行けるだけ行って観られるだけ観る。
行けるだけ行って観られるだけ観る。
最初に観たのは『網走番外地』。どうせ雪だからとモノクロで撮った人気シリーズの第1弾である。
網走刑務所には実際に行ったけど(博物館網走監獄 →2012.8.19)、きちんと現地でロケをやっていて満足。
特筆すべきはアクションをはじめとする映像の迫力で、確かにすごくて思わず手に汗握ってしまう。
いや、むしろこの映画は、チェーンデスマッチ脱獄アクションをやりたいがための方便なのだ。
正直なところストーリーは明らかに二の次で、どうアクションに持ち込むかということでつくられている。
『ダーティーハリー』がやりたいアクションを詰め込んだだけ(→2020.5.23)なのと似ていると思う。
でもできあがったアクションの迫力が圧倒的なので、当時の観客が熱狂したのは十分理解できる。
健さん演じる主人公は恵まれない環境と短気な性格でどんどん堕ちていくわけだが、それがなんとももどかしい。
せっかくアラカンが助けてくれたのによーそっち行っちゃいかんだろーと気が気でない展開に巻き込まれていく。
どうしてもそれが気になってしまう僕は、現代社会のコンプライアンスに毒されているのか?とちょっと思った。
まあ古今東西、抗えない不幸に翻弄されるのはドラマの基本なので(→2005.6.9)、素直に乗っかるべきだろうけど。
今の感覚だと設定と展開に昭和の大らかさを感じてしまう。これはハッピーエンドなのか?と首をひねりつつ終了。
でもシリーズが10作もつくられた大ヒットとなったからには、当時はそれでよかったわけだ。時代は変わったってことか。
また、貧しさの強調が気になる。われわれはその苦しみを現代では信じられないものとして本気で重く受け止めるけど、
昭和の感覚だとけっこう「あるある」だったのかもしれない。陥りやすいワンオヴゼムの不幸。みんな貧しかったのだ。
そんなわけで「昭和とはどんなだったか」をかなり考えさせられる機会となったのであった。社会学的高倉健の世界。
 『網走番外地』撮影中のすごくいい写真が展示されていた。
『網走番外地』撮影中のすごくいい写真が展示されていた。
劇場は丸の内TOEIなのだが、有楽町のビルの地下で映画ってこと自体、かなり昭和な体験だなあとあらためて思う。
そしてリヴァイヴァル上映を気軽に堪能できる、都会暮らしの恩恵の大きさを思う。贅沢な楽しみをさせてもらっている。
ロビーにはさまざまな健さん関連資料が展示されており、たいへん興味深い。若い健さんは本当にイケメンなのである。



L: 若き日の健さんの写真(トリミング)。こちらは「夏休みの旅行」。うーん、若い。そしてかっこいい。
C: 「撮影所内にて健さんのファンの方々に囲まれて」(トリミング)。さすがにイケメンですなあ。
R: 「二期生全員でのクリスマス」(トリミング)。東映ニューフェイスですな。いま見るとすごく新鮮。
 「撮影の待ち時間のほっと一息のティータイム」(トリミング)。
「撮影の待ち時間のほっと一息のティータイム」(トリミング)。



L: ロビーに展示されていたポスター。 C: 健さんグッズも展示。 R: 刺青のデザイン画。職人芸である。
というわけで、これからしばらくどっぷりと健さんの世界に浸る日々が続くのだ。楽しみである。
■2024.11.6 (Wed.)
トランプが勝ったというかハリスと民主党が負けたというか。また騒がしい4年間が始まるのか。
■2024.11.1 (Fri.)
MacBook Airの変換機能についにブチ切れて、サブスクだけどATOKを入れちゃうのであった。
とにかく顔文字が邪魔だったし、変換もありえない候補が先に来るしでいちいちムカついていたのだが、
解放されて本当に快適である。おかげで旧浅草区編(→2020.12.26)を一気に書き上げることができた。
これで2020年の日記はすべて完了! 明日からは2021年の分を書いていくのだ! 年末までは負債が3年分になったぜ!
diary 2024.10.
diary 2024
index